すららはうざい!?すららが選ばれるおすすめのポイントを紹介します
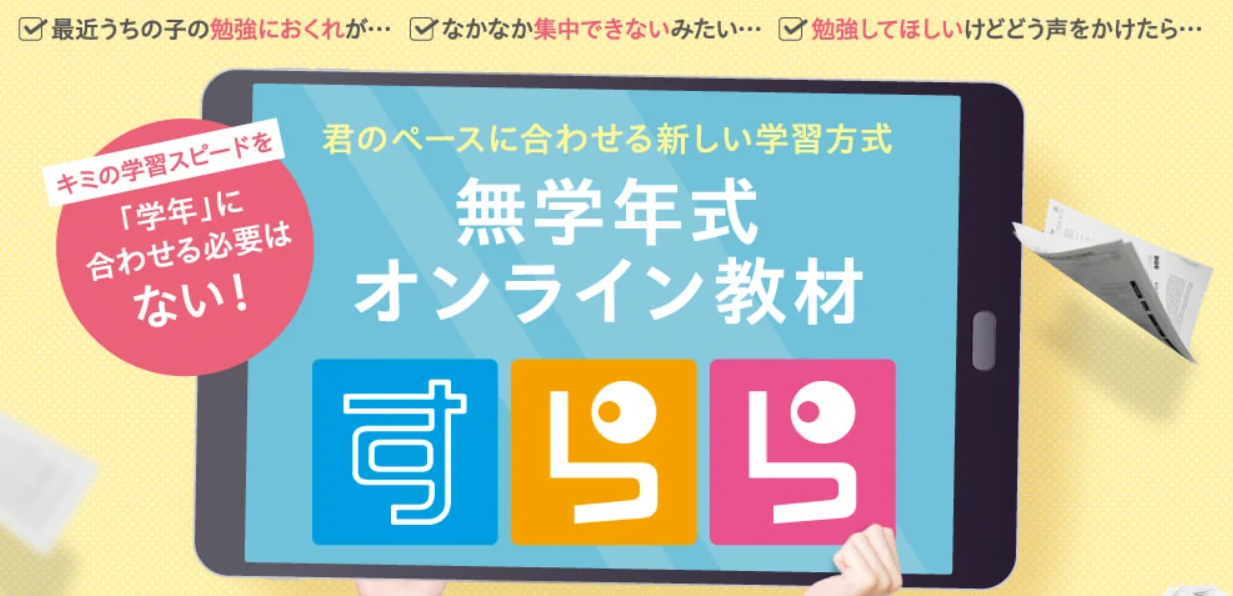
オンライン学習教材「すらら」は、多くの家庭で利用されている人気のサービスです。
しかし、検索すると「すらら うざい」といったネガティブなワードを目にすることもあります。
実際のところ、すららにはどんな特徴があり、なぜ選ばれているのでしょうか?この記事では、すららのおすすめポイントを詳しく紹介します。
学習スタイルや機能を知ることで、すららが自分やお子さんに合っているかどうか判断する手助けになればうれしいです。
すららのおすすめポイントをまとめました
すららには、一般的なオンライン学習サービスとは異なる特徴がいくつもあります。
学年にとらわれない学習スタイルや、アニメキャラクターとの対話型授業、さらには学習管理をサポートする「すららコーチ」など、ユニークな仕組みがたくさんあります。
ここでは、すららのおすすめポイントを詳しく見ていきましょう。
| ポイント | 具体例 |
| 無学年式 | 小1の子が中学英語も学べる!苦手もじっくり戻れる |
| 対話型授業 | アニメキャラとの対話形式で「双方向」学習 |
| すららコーチ | 親がスケジュール管理しなくてOK!丸投げ可能 |
| 発達障害・不登校対応 | AIがつまずきを解析→無理なく学習再開できる |
| 成果が見える | テスト・レポート・定着診断で、親も安心 |
| 英語3技能対応 | 話す・聞く・読むがまんべんなく学べる |
| 兄弟OK | 1契約で複数人OK→家族で使えば超コスパがいい |
ポイント1・無学年式!学年に縛られず、得意も苦手も自由に学べる
すららの最大の特徴の一つが「無学年式」の学習システムです。
学校の授業は学年ごとに決められた内容を学ぶため、得意な教科があっても「もっと先へ進みたい」と思っても制限があります。
逆に、苦手な教科がある場合は「わからないまま進んでしまう」ことになりがちです。
しかし、すららなら学年の枠を超えて学ぶことができるので、得意も苦手も自分のペースで学習を進められます。
学力や進度に関係なく、自分のペースで学べる
無学年式の魅力は、子ども一人ひとりの学力や理解度に合わせて勉強できることです。
たとえば、小学校低学年の子が中学レベルの英語を学ぶことも可能ですし、中学2年生が小学校の算数に戻って復習することもできます。
学校の授業についていけなくて苦しむことも、逆に簡単すぎて退屈することもなく、最適なレベルの学習を続けることができます。
「得意はどんどん進める」「苦手はじっくり戻る」が簡単にできる
すららでは、得意な教科はどんどん進め、苦手な教科はしっかりと復習することができます。
たとえば、算数が苦手な場合、小学校の基礎からじっくり学び直し、つまずきを解消してから次に進めます。
逆に、得意な教科は学年の枠を超えて学ぶことができるため、学習のモチベーションも維持しやすいです。
こうした柔軟な学習スタイルが、すららの大きな魅力です。
ポイント2・「対話型アニメーション授業」で、わかりやすい&飽きない
オンライン学習は、自宅で自分のペースで進められる反面、飽きてしまったり、集中力が続かなかったりすることがあります。
しかし、すららの授業は「対話型アニメーション授業」なので、まるで先生と会話しているような感覚で学習を進められます。
アニメーションを活用することで、子どもが学習に興味を持ちやすく、継続しやすいのが特徴です。
アニメキャラが「先生役」として、子どもと会話しながら進めてくれる
すららでは、アニメキャラクターが先生の代わりとなり、授業を進めてくれます。
単なる映像授業とは異なり、キャラクターが質問を投げかけたり、ヒントを出したりしながら進行するため、双方向のやりとりが生まれます。
「ただ聞くだけの授業だと集中できない」という子どもでも、キャラクターとの会話を通じて楽しく学ぶことができます。
難しいことも「図や動き」で視覚的に理解できる
文章だけでは理解しにくい概念も、すららではアニメーションや図解を使ってわかりやすく説明してくれます。
たとえば、算数の「分数の足し算」や理科の「電気の流れ」といった抽象的な内容も、アニメーションで具体的に示されることで、視覚的に理解しやすくなります。
特に、暗記が苦手な子やイメージで学ぶのが得意な子にとって、大きな助けになります。
キャラが褒めてくれるからやる気UP!飽きっぽい子でも続きやすい
学習のモチベーションを維持するのは簡単ではありませんが、すららではアニメキャラクターが適度に褒めてくれるため、子どもが「もっと頑張ろう!」という気持ちになりやすいです。
「ここまでできたね!」「あと少しでクリアできるよ!」といった声掛けがあることで、達成感を感じながら学習を続けることができます。
特に、飽きっぽい子や自主学習が苦手な子にとって、続けやすい仕組みになっています。
ポイント3・「すららコーチ」がついて親の負担が激減
オンライン学習を続ける上で、親の負担が大きくなりがちなのが「学習管理」です。
「ちゃんと勉強しているか」「どのくらい進んでいるか」「苦手はどこなのか」など、親がすべて把握するのは大変です。
しかし、すららには「すららコーチ」という専任の学習サポートがついており、親が細かく管理しなくても大丈夫な仕組みになっています。
プロの「すららコーチ」が学習計画を作成&フォローしてくれる
すららコーチは、子ども一人ひとりの学習状況に応じて、最適な学習計画を立ててくれます。
「どこから勉強すればいいのかわからない」「進め方に迷ってしまう」といった不安があっても、プロのコーチが計画を立ててくれるので安心です。
定期的に進捗をチェックし、学習のペースを調整してくれるため、無理なく続けることができます。
子どもの特性や希望に合わせたオーダーメイド学習計画を立ててくれる
すららの学習計画は、画一的なものではなく、子どもの理解度や学習スタイルに合わせて作られます。
たとえば、「苦手な算数を重点的に復習したい」「英語を先取りで進めたい」といった希望に応じて、オーダーメイドの学習プランを作成してくれます。
発達障害や不登校の子どもにも対応できるように、無理のないペースで学べるのが魅力です。
質問や相談はコーチに直接できるから親は見守るだけでOK
すららコーチには、学習の悩みや進め方について直接相談することができます。
たとえば、「この単元がどうしても理解できない」「やる気が続かない」といった場合でも、コーチが適切なアドバイスをしてくれるので安心です。
親が毎日学習をチェックしたり、スケジュールを管理したりする必要がなくなるため、共働きの家庭や忙しい親御さんにとっても助かる仕組みです。
ポイント4・発達障害・不登校にも対応!学習への不安を取り除いてくれる
すららは、一般的な学習教材とは異なり、発達障害や不登校の子どもにも対応できるよう設計されています。
「学校の授業についていけない」「集団学習が苦手」「学習に対する不安がある」といった悩みを抱える子どもにとって、安心して学べる環境が整っています。
実際に、多くの教育機関でも導入され、効果が認められています。
文部科学大臣賞も受賞している学習支援ツール
すららは、その学習支援の仕組みが高く評価され、文部科学大臣賞を受賞しています。
これは、単なるオンライン教材ではなく、「子ども一人ひとりの学びを支えるツール」としての実績が認められた証です。
個別最適な学習ができる仕組みが、全国の学校や教育機関でも活用されています。
発達障害(ADHD、学習障害など)の子にも適した設計で安心
発達障害のある子どもは、集中力が続かなかったり、決められた学習ペースに合わせるのが難しかったりすることがあります。
すららは、そうした特性を考慮し、自分のペースで進められる無学年式を採用。
さらに、アニメーション授業や適切なフィードバックを活用し、学習へのハードルを下げる工夫がされています。
無理なく学習を継続できる設計になっているので、安心して取り組めます。
不登校で学校の授業に追いつけない子でも取り組みやすい
不登校の子どもにとって、学校の授業についていくことは大きな負担になります。
「どこから勉強すればいいのかわからない」「久しぶりに勉強すると、難しく感じてしまう」といった不安を抱えることもあります。
すららでは、学年に関係なく自分に合ったレベルから学習できるため、無理なく学びを再開できます。
また、授業の進行がアニメキャラとの対話形式で進むため、先生やクラスメイトと話すことに抵抗がある子どもでも安心して学習できます。
つまずきをAIが解析→理解不足の箇所を自動で出題してくれる
すららには、AIによる「つまずき解析」機能が搭載されています。
学習の進捗や間違えた問題を分析し、どの部分の理解が不足しているのかを自動で判断。
苦手な単元を重点的に復習できるように、適切な問題を出題してくれます。
これにより、効率よく学習を進めることができ、確実に理解を深めることができます。
ポイント5・オンラインテスト&リアルタイム学力分析で、成果が見える
「どれくらい理解できているのか」「苦手なポイントはどこか」といった学習の成果が目に見えると、やる気の維持にもつながります。
すららでは、オンラインテストやAIによる学力分析機能を活用し、学習の定着度をしっかりチェックできます。
これにより、効率よく勉強を進めることが可能になります。
小テストで間違えた問題を即フィードバックできる
すららでは、授業の後に小テストを実施し、その場で理解度を確認できます。
間違えた問題はすぐにフィードバックされ、どこを間違えたのか、どう解き直せばいいのかを学ぶことができます。
この仕組みにより、復習の効率が上がり、学習内容をしっかり定着させることができます。
定着度診断でAIがどこが苦手か把握し即対策問題を出してくれる
「なんとなく勉強しているけど、実際にどこが苦手かわからない」といった悩みを解決するのが、すららのAIによる「定着度診断」です。
テスト結果をもとに、どの単元が弱いのかを自動で分析し、対策問題を出題してくれます。
これにより、ただ勉強をこなすだけでなく、「どの部分を重点的に学ぶべきか」を明確にしながら学習を進められます。
保護者にもレポート配信し「何をどこまで理解しているのか」をしっかり確認できる
子どもがどのくらい勉強しているのか、どの分野が得意で、どこが苦手なのかを知りたい親御さんも多いのではないでしょうか。
すららでは、学習状況をまとめたレポートが保護者に配信されるため、子どもの進捗を簡単に確認することができます。
親が直接教えたり、毎回細かくチェックしなくても、レポートを見れば「どこをサポートすればいいのか」が分かるので安心です。
ポイント6・英語が「リスニング」「リーディング」「スピーキング」の3技能対応
すららの英語学習は、「リスニング」「リーディング」「スピーキング」の3技能をバランスよく鍛えることができます。
一般的なオンライン教材では「リーディング」と「文法」が中心になりがちですが、すららではネイティブ音声や音読チェックを活用し、実践的な英語力を身につけられるのが特徴です。
英検対策としてもおすすめで、基礎からしっかり学びたい人にぴったりの学習システムです。
ネイティブ音声のリスニングを学ぶことができる
英語のリスニング力を鍛えるためには、ネイティブの発音をたくさん聞くことが大切です。
すららでは、ネイティブスピーカーによる音声を使用し、正しい発音やイントネーションを自然に身につけることができます。
学校の授業だけではリスニングに自信が持てない子も、すららを活用することで耳を慣らし、英語の音に対する抵抗を減らすことができます。
音読チェックでスピーキング練習ができる
「英語を話せるようになりたいけど、どう練習すればいいかわからない」と感じる人も多いのではないでしょうか。
すららでは、音読チェック機能を活用してスピーキングの練習ができます。
発音を確認しながら話すことで、自然な英語のリズムやイントネーションを習得することが可能です。
単に「読む」「聞く」だけでなく、「実際に発音する」機会があるため、スピーキング力も着実に伸ばすことができます。
単語・文法もアニメーションで丁寧に解説してくれるから英検対策におすすめ
すららの英語学習では、単語や文法の学習もアニメーションを使ってわかりやすく解説してくれます。
文字だけの説明では理解しにくい内容も、視覚的に学ぶことでスムーズに身につけることができます。
また、英検対策としても活用しやすく、基礎から応用まで幅広く学習できるため、英語に苦手意識がある子でも安心して取り組むことができます。
ポイント7・料金体系が「1人分じゃない!」兄弟OK&科目追加自由
すららは、他のオンライン学習サービスと比べてコストパフォーマンスが高いのも魅力の一つです。
通常のオンライン教材では、子ども1人につき1つの契約が必要な場合が多いですが、すららは「1契約で兄弟も一緒に使える」という独自の料金体系を採用しています。
さらに、必要な科目だけを選んで追加できるので、無駄なく利用できるのも嬉しいポイントです。
1つの契約で兄弟同時利用OK!(人数分の追加料金なし)
一般的なオンライン学習サービスでは、兄弟が利用する場合、それぞれのアカウント分の料金が発生することが多いです。
しかし、すららは1契約で兄弟も一緒に利用することができるため、家族にとって経済的な負担が少なくなります。
「兄と妹で一緒に使いたい」「下の子が後から使うかもしれない」といった家庭にもぴったりです。
小学生の兄と中学生の妹、同じ契約内で利用できるからコスパがいい
学年が異なる兄弟がいる家庭では、「小学生用と中学生用、両方契約しなければならないのでは?」と心配になるかもしれません。
しかし、すららは無学年式の教材のため、小学生でも中学生の内容を学ぶことができます。
たとえば、「小学生の兄は算数を先取り」「中学生の妹は苦手な数学を復習」といった使い方ができるため、非常にコストパフォーマンスが良いです。
科目ごとに選んで追加できるから、無駄がない
「この教科だけ学びたい」というニーズに応えられるのも、すららの強みです。
通常のオンライン教材では、「セット料金」で全教科が含まれていることが多いですが、すららでは必要な科目だけを選んで追加することが可能です。
たとえば、「英語だけ強化したい」「数学と国語を重点的に学びたい」といった要望に合わせてカスタマイズできるので、無駄なく効率よく学習を進めることができます。

【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材にはないすららのメリットについて
家庭用タブレット教材はさまざまな種類がありますが、「すらら」は他の教材とは一線を画す特徴を持っています。
「すららはうざい?」という声を聞くこともありますが、実際には多くの家庭で高い評価を受けている学習ツールです。
その理由として、すららには「学習コーチのサポート」や「不登校・発達障害への対応」など、他の教材にはないメリットがあるからです。
ここでは、すららならではのメリットについて詳しく解説していきます。
メリット1・対人サポート付き!「すららコーチ」がある
家庭用タブレット教材の多くは、基本的に子どもが自分で学習を進めるスタイルが主流です。
しかし、すららでは「すららコーチ」という学習サポートのプロがつき、子どもの学習をフォローしてくれる仕組みがあります。
親が細かくスケジュールを管理したり、進捗をチェックしたりしなくても、すららコーチがしっかりサポートしてくれるので、忙しい家庭でも安心です。
すららはプロの学習コーチが進捗を管理してくれる
すららコーチは、子どもの学習状況を定期的にチェックし、進捗を管理してくれます。
特に、オンライン学習では「どこまで勉強が進んでいるのか」「苦手な部分はどこか」が分かりにくく、親がサポートするのが大変な場合があります。
しかし、すららコーチが学習のペースを見守り、必要に応じてアドバイスをくれるため、子どもがスムーズに学習を進められる環境が整っています。
コーチが学習スケジュールを子どもに合わせて作成してくれる
すららでは、一人ひとりの学習状況や性格に合わせたオーダーメイドの学習スケジュールを作成してくれます。
例えば、「算数は得意だからどんどん先取りしたい」「国語は苦手だからゆっくり進めたい」といった個別のニーズに対応してくれるのが特徴です。
また、学習の進み具合に応じてスケジュールを調整してくれるため、無理なく続けられるのもメリットです。
メリット2・不登校・発達障害対応に特化している
すららは、一般的な家庭用タブレット教材と異なり、不登校や発達障害の子どもにも対応できる仕組みが整っています。
「学校に行けなくても勉強を続けたい」「学習の遅れを取り戻したい」という子どもにとって、すららは強い味方となります。
文部科学省にも認められ、多くの学校で導入されている実績があります。
不登校や発達障害の子向けに、文科省推薦教材として採用されてる実績がある
すららは、文部科学省が推奨する学習教材として採用されている実績があります。
特に、不登校や発達障害を持つ子どもの学習支援に力を入れており、全国の学校や教育機関でも活用されています。
学校の授業についていくのが難しい子どもでも、自分のペースで学習を進めることができるため、安心して学べる環境が整っています。
不登校児童に対して「出席扱い」される学校も多い
すららを導入している学校の中には、「すららで学習することで、出席扱いになる」ケースも増えています。
これは、すららが学校のカリキュラムに沿った内容を提供しており、教育機関としても「学習を継続している」と判断できるためです。
不登校の子どもにとって、「学校に行けない=勉強が遅れる」という不安を解消することができ、安心して学習を進めることができます。
ASD・ADHD・LD(学習障害)に合わせたカリキュラム&サポートが受けられる
すららは、発達障害(ASD・ADHD・LD)を持つ子どもが学習しやすいように設計されています。
たとえば、以下のような特徴があります。
– **視覚的に理解しやすいアニメーション授業**
→ 文章を読むのが苦手な子でも、アニメーションを活用した授業で直感的に学べる。
– **集中力が続かない子のために短時間で区切れる学習**
→ 1回の授業が短く、適度に休憩を挟めるので、集中力が持続しやすい。
– **学習のつまずきをAIが解析し、苦手な部分を自動で出題**
→ 自分の苦手分野をピンポイントで学習できるため、効率よく知識を定着させられる。
このように、すららは発達障害のある子どもでも無理なく学習を進められる環境を提供しています。
メリット3・学年を超えた「無学年学習」ができる
すららの大きな特徴の一つが「無学年学習」です。
学校のカリキュラムでは学年ごとに決められた範囲を学ぶ必要がありますが、すららなら学年に関係なく自由に学習を進められます。
これにより、得意な科目はどんどん先取りし、苦手な分野は基礎からじっくり復習することが可能です。
自分のペースで学べるため、無理なく着実に学力を伸ばすことができます。
学年関係なく自由にさかのぼり・先取りできる
すららでは、苦手な単元を前の学年に戻って復習したり、得意な分野はどんどん先に進めたりすることができます。
たとえば、小学6年生が中学の数学を学んだり、中学2年生が小学校の漢字を復習したりと、自分に合った学習プランを柔軟に組めるのが特徴です。
「学校の授業についていけない」「もっと先の内容を学びたい」といった悩みを解決し、一人ひとりに合った学習ができるのは大きなメリットです。
発達障害の子は「つまずいたまま進まない」からマイペースに進められるのはポイント
発達障害を持つ子どもにとって、学校の授業ペースについていけないことが大きなハードルになります。
すららの無学年学習なら、つまずいた部分を何度でも復習できるため、理解が不十分なまま次へ進むことがありません。
「わからないまま授業が進むとついていけなくなる」という不安がなくなり、安心して学習を続けることができます。
マイペースに進められる環境は、学習に苦手意識を持っている子どもにとって大きな助けになります。
メリット4・AI診断×対人コーチングで学習設計が精密
すららでは、AIを活用した学習診断と、すららコーチによる対人サポートを組み合わせた「Wサポート体制」を採用しています。
多くのオンライン学習サービスはAIによる自動管理が中心ですが、すららはAIだけでなく、コーチが個別に学習状況を確認し、調整してくれるのが特徴です。
これにより、より精密な学習設計が可能になります。
AI+人間コーチのWサポートはすららだけのポイント
AIは、正答率や学習履歴を分析し、苦手分野や理解度を判断するのに優れていますが、学習のモチベーション管理や細かい指導は難しい部分もあります。
そこで、すららではAIの客観的なデータ分析に加え、すららコーチが個別に学習計画をサポートすることで、より効果的な学習環境を整えています。
AIと人間のダブルサポートにより、学習の質が向上し、より効率的に知識を定着させることができます。
AIだけではフォローしきれない細かい学習状況を、コーチが調整してくれる
AIは、子どもの正答率や学習履歴をデータとして分析し、苦手な単元を特定するのに役立ちますが、「なぜその単元が苦手なのか」「どのようなアプローチが効果的なのか」といった部分までは判断できません。
すららコーチは、こうしたAIの分析結果をもとに、個別の学習状況や特性を考慮しながら適切なフォローをしてくれます。
たとえば、「文章題は苦手だけど計算は得意」「漢字の暗記が苦手なので復習が必要」といった細かい状況を見極め、学習プランを柔軟に調整してくれるのがすららの強みです。
メリット5・紙を使わず、すべてデジタルでも「記述力」が鍛えられる
オンライン学習では、どうしても「読む・選ぶ」といったインプット型の学習が中心になりがちです。
しかし、すららでは「論理的に考えて書く力」や「説明する力」を養うことにフォーカスしたカリキュラムが組まれており、デジタル学習でありながら記述力を鍛えることができます。
これにより、単に知識を覚えるだけでなく、思考力や表現力の向上にもつながります。
「論理的に書く力」「説明する力」にフォーカスしたカリキュラム
すららの学習プログラムには、単なる暗記ではなく、「なぜそうなるのか」「どのように説明できるか」といった論理的思考を求める問題が組み込まれています。
特に国語の読解問題や、数学の文章題の解き方を説明するような問題では、自分の言葉で答えを表現する力が必要になります。
これにより、テストや受験で重要視される「記述力」も自然と鍛えられるのが特徴です。
読解+記述のトレーニングがデジタル完結でできる教材は珍しい
一般的なデジタル教材では、記述問題に対応しているものは少なく、記述力を鍛えるには紙のドリルを併用する必要があることが多いです。
しかし、すららならデジタル環境だけで読解力と記述力のトレーニングが可能です。
特に、文章を読んで「要約する」「考えを説明する」問題が充実しており、デジタル学習だけでも十分な記述練習ができるのがすららの大きなメリットです。
メリット6・途中でやめても「再開」がしやすい
学習を継続することは理想ですが、子どもによっては途中で学習を休んでしまうこともあります。
すららでは、一度学習を中断しても簡単に再開できる仕組みが整っており、再び学習を始めるときのハードルが低くなっています。
特に、不登校や発達障害の子どもにとっては、「学習ペースに波がある」ことが多いため、自由に休んで戻れる環境は大きな安心材料となります。
すららは一時中断→復帰が簡単にできる
すららでは、学習履歴がすべてデータで管理されているため、途中で学習を中断しても、次に再開するときにどこから始めればいいのかがすぐにわかります。
また、無学年学習のシステムがあるため、決まったカリキュラムに縛られず、必要な部分から学び直せるのも魅力です。
「しばらく休んでいたけど、また勉強を再開したい」という場合でも、スムーズに復帰できるのがすららの強みです。
不登校や発達障害の子は「学習ペースに波がある」から、自由に休んで戻れる環境は重要
不登校や発達障害を持つ子どもにとって、毎日決まったペースで学習を続けることが難しいケースも多いです。
そのため、「調子がいいときに勉強して、疲れたら休む」といった柔軟な学習スタイルが求められます。
すららなら、いつでも好きなタイミングで学習を始められ、休んでも学習の進度がリセットされることはありません。
自分のペースで学べる環境が整っているため、無理なく続けることができます。
メリット7・出席認定・教育委員会との連携実績がある
すららは、単なる家庭用学習教材ではなく、教育委員会や学校とも連携し、不登校支援の一環として活用されている実績があります。
特に、すららを利用することで「出席扱い」として認められるケースが増えており、不登校の子どもが学習を続けながら学校とのつながりを保てる仕組みが整っています。
すららを使っていると「出席扱い」として学校が認めるケースが多数
文部科学省のガイドラインでは、不登校の児童生徒がICTを活用して学習を継続した場合、一定の条件を満たせば「出席扱い」とすることができるとされています。
すららは、この条件を満たす教材として、多くの学校で「出席扱い」と認められています。
そのため、学校に通えない状況でも、すららを使って学習を続けることで、学籍を維持しながら学ぶことが可能です。
不登校支援教材として、学校や病院と連携しているのはすららならでは
すららは、単なるオンライン教材ではなく、学校や教育機関、病院とも連携しながら、不登校の子どもたちの学習支援を行っています。
特に、病気や発達障害が原因で通学が難しい子どもたちに対し、学校と協力しながら学習支援を提供しているケースもあります。
こうした取り組みは、一般的なタブレット学習教材にはない特徴であり、「学校とのつながりを持ちながら学べる環境」を提供している点で、大きなメリットとなっています。

【すらら】はうざいと言われる原因は?すららのデメリットについて紹介します
すららは多くの家庭で活用されているオンライン学習教材ですが、一部では「すららはうざい」と感じる声もあります。
どんな教材にもメリットとデメリットがあり、人によっては合わないと感じることもあるでしょう。
ここでは、すららが「うざい」と言われる原因や、デメリットについて詳しく解説していきます。
原因1・すららコーチやサポートからの連絡がしつこいと感じることがある
すららの大きな特徴のひとつが、「すららコーチ」による学習サポートです。
学習計画を立ててくれたり、進捗を管理してくれたりと、学習の継続をサポートする仕組みが整っています。
しかし、人によっては「サポートがしつこい」と感じることもあるようです。
自主的にやりたい子や、放っておいてほしい子には合わないこともある
すららコーチは、子どもの学習状況に応じてアドバイスを送ったり、進捗を確認したりするため、定期的に連絡が入ります。
これは、「学習習慣がついていない子どもにとってはありがたいサポート」ですが、一方で「自分のペースで勉強したい」「誰にも干渉されたくない」と思っている子どもにとっては、煩わしく感じることがあるかもしれません。
また、親としても「頻繁に連絡がくるのが面倒」「もっと自由に学ばせたい」と思う場合は、少しストレスになることもあるでしょう。
こうした点をデメリットと感じるかどうかは、家庭の学習方針や子どもの性格による部分が大きいです。
原因2・「やらされ感」が強くなるとプレッシャーに感じることがある
すららはAIを活用して学習計画を自動作成し、最適な学習ステップを提案してくれます。
この仕組み自体は非常に便利ですが、人によっては「自分で学習を決める自由が少ない」と感じることもあるようです。
自動で学習計画を作ってくれるAIに縛られていると感じてしまうことがある
すららのAIは、過去の学習履歴やつまずいたポイントを分析し、「次にどの単元を勉強すべきか」を提案してくれます。
しかし、それが「やらされている」と感じる子どももいるかもしれません。
例えば、「今日は国語をやりたいのに、AIの指示では数学になっている」といった場合、計画通りに進めなければならないことがプレッシャーになり、逆に学習のモチベーションが下がってしまうこともあります。
また、学習計画を守れなかったときに「遅れている」と感じてしまうことで、焦りやストレスにつながるケースもあるようです。
こうした点を考えると、すららは「決められたスケジュール通りに学習するのが苦手な子」や「自分のやりたいことを優先したい子」には、少し合わない部分があるかもしれません。
このように、すららには手厚いサポートやAI学習のメリットがある一方で、「干渉されすぎるのが苦手」「自由度の高い学習スタイルが好き」という子どもには、デメリットに感じることもあるかもしれません。
とはいえ、すららの学習スタイルが合うかどうかは、実際に試してみないとわからない部分もあるので、無料体験を活用して、子どもに合っているかを確認するのがおすすめです。
原因3・キャラクターやナビゲーションが子どもっぽい・くどいと感じることがある
すららは、アニメーションを活用した対話型の授業が特徴ですが、このスタイルが合わないと感じる子どももいるようです。
特に高学年や思春期の子どもにとっては、「キャラクターの話し方がくどい」「子どもっぽい」と思うことがあるかもしれません。
高学年や思春期の子にはキャラクターがうざいと感じることがある
すららの授業は、アニメキャラクターがナビゲートする形式で進行します。
小学生の低・中学年の子どもにとっては親しみやすく、学習意欲を高める工夫がされていますが、高学年や中学生・高校生になると「子どもっぽい」「キャラクターの口調が気になる」と感じることもあります。
また、「シンプルに解説してほしいのに、キャラクターのやり取りが長く感じる」といった声もあり、スムーズに学習を進めたい子どもにとってはストレスになる可能性があります。
そのため、すららを利用する際は、子どもの年齢や性格に合うかどうかを事前に確認することが大切です。
原因4・勧誘や営業の印象が「しつこい」と感じる人がいる
すららは、公式サイトやSNS広告を通じて積極的に宣伝を行っています。
そのため、興味を持って資料請求や無料体験を申し込んだ後に、「電話やメールが頻繁に来る」と感じる人もいるようです。
特に、「一度断ったのに、再び連絡が来た」といったケースでは、SNS上で「しつこい」「うざい」といった声が見られることがあります。
「連絡が頻繁」と感じると、SNSでは「うざい」と言われることがある
すららの勧誘が「しつこい」と感じるかどうかは、個人差があります。
サポート体制が充実しているという見方もできますが、「もう少し距離を置いてほしい」「自分のペースで検討したい」という人にとっては、頻繁な連絡が負担に感じることがあるかもしれません。
とはいえ、すらら側としても「入会を迷っている人へのフォロー」という目的で連絡をしているため、不要な場合は「もう連絡はいりません」とはっきり伝えることで解決できることがほとんどです。
原因5・料金が高く感じる割に効果が実感できない場合がある
すららの料金は、他のオンライン学習サービスと比べると高めに設定されています。
無学年式・AI分析・すららコーチのサポートなど、充実した機能があるためその分のコストがかかるのは当然ですが、実際に効果を実感できない場合、「費用に見合わない」と感じる保護者もいるようです。
子供が1人で学習に取り組めないままだと勉強効果を実感できない保護者もいる
すららは「一人で学習を進められる」ことを前提としたシステムですが、子どもによっては「やる気が続かない」「親がサポートしないと取り組めない」というケースもあります。
そうなると、「せっかく料金を払ったのに、学習が進まない」「効果が感じられない」といった不満につながることも。
また、すららは学習の継続が大切な教材なので、「最初のうちは頑張っていたけど、途中でやめてしまった」という場合も、費用に対して満足感が得られないかもしれません。
この点については、すららコーチのサポートを活用しながら、親も適度に声かけをしてあげることで、学習の継続につなげることができるでしょう。
このように、すららには「合わないと感じるポイント」もいくつかありますが、これはどんな学習サービスにも言えることです。
すららを検討する際は、メリット・デメリットをよく理解した上で、お子さんに合った学習スタイルかどうかを見極めることが大切です。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは高い?すららの料金プランについて紹介します
すららは、AI学習や無学年学習、すららコーチによるサポートが特徴の家庭用タブレット教材です。
しかし、その機能の充実度から「料金が高いのでは?」と感じる人も多いかもしれません。
実際、他のタブレット教材と比較すると、すららはやや高めの価格設定になっていますが、その分の価値があるのか、具体的な料金プランとあわせて詳しく紹介していきます。
すらら家庭用タブレット教材の入学金について
すららを利用するには、初回に入学金が必要になります。
コースによって入学金が異なるため、以下の表を参考にしてください。
| コース名 | 入学金(税込) |
| 小中・中高5教科コース | 7,700円 |
| 小中・中高3教科、小学4教科コース | 11,000円 |
入学金は一度だけの支払いですが、他のオンライン学習サービスでは入学金が不要なところもあるため、「初期費用がかかる」と感じる人もいるかもしれません。
しかし、すららは無学年学習が可能で、学年を超えて学べる点を考えると、長く続けるほどお得になる仕組みといえます。
すらら家庭用タブレット教材/3教科(国・数・英)コース月額料金について
すららの3教科コースは、国語・数学(算数)・英語の3科目を学べるプランです。
料金プランには「毎月支払い」と「4ヵ月継続」の2種類があります。
毎月支払いコースの料金
| コース名 | 月額 |
| 小中コース | 8,800円 |
| 中高コース | 8,800円 |
4ヵ月継続コースの料金
| コース名 | 月額 |
| 【4ヵ月】小中コース | 8,228円 |
| 【4ヵ月】中高コース | 8,228円 |
4ヵ月継続コースを選ぶと、毎月支払いコースよりも月額料金が少し安くなります。
すぐに解約する可能性が低い場合は、継続コースを選んだほうがコストを抑えられます。
すらら家庭用タブレット教材/4教科(国・数・理・社)コース月額料金について
理科・社会を含めた4教科コースは、小学生向けに用意されています。
| コース名 | 月額 |
| 小学コース(毎月支払いコース) | 8,800円 |
| 小中コース(4ヵ月継続コース) | 8,228円 |
3教科コースとほぼ同じ価格帯になっており、理科・社会も含めて学びたい場合は、4教科コースを選ぶのがおすすめです。
すらら家庭用タブレット教材/5教科(国・数・理・社・英)コース月額料金について
5教科コースは、小学校・中学校・高校の全学年の範囲をカバーし、無学年学習を活かしながら幅広く学べるプランです。
毎月支払いコースの料金
| コース名 | 月額 |
| 小学コース | 10,978円 |
| 中高コース | 10,978円 |
4ヵ月継続コースの料金
| コース名 | 月額 |
| 【4ヵ月】小中コース | 10,428円 |
| 【4ヵ月】中高コース | 10,428円 |
5教科すべてを学びたい場合は、やはり毎月支払いコースよりも4ヵ月継続コースのほうが料金が抑えられるため、おすすめです。
### すららの料金は高い?それとも妥当?
すららの月額料金は、他の家庭用タブレット教材と比較するとやや高めに感じるかもしれません。
しかし、その分、以下のような強みがあります。
– **無学年式の学習**ができ、学年に縛られず自由に進められる
– **すららコーチのサポート**があるため、学習計画を親が管理しなくてもOK
– **AI診断機能**により、苦手分野を自動で分析してくれる
– **兄弟での利用OK**(1契約で複数の子どもが使える)
これらの点を考慮すると、「長期的に続けるならコスパが良い」と感じる人も多いです。
一方で、「短期間だけ利用したい」「自分で計画的に勉強できる」という場合は、もう少し安価な学習教材を検討するのもよいかもしれません。
すららの料金が高いと感じるかどうかは、どのような学習サポートを求めるかによって変わります。
まずは無料体験を試し、お子さんに合った学習スタイルかどうかを確認するのがよいでしょう。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの勉強効率や勉強効果は?コースについて紹介します
すららは、無学年式のオンライン学習教材として、幅広い学年の子どもたちに活用されています。
しかし、「本当に勉強効率がいいの?」「効果があるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
特に、すららの3教科コース(国語・数学・英語)は、基礎力の定着を重視し、短時間でも効率よく学べるカリキュラムが特徴です。
ここでは、すらら3教科コースの具体的な勉強効果について詳しく紹介します。
すらら3教科コース(国・数・英語)の勉強効果について紹介します
すららの3教科コースは、特に基礎学力をしっかり固めたい人や、定期テストで成果を出したい人に向いているコースです。
オンライン学習の中でも、対話型授業やAIによるつまずき解析を活用することで、「短時間で効率よく学ぶ仕組み」が整っています。
勉強効果1・基礎力の定着がとにかく早い
すららは、AIを活用した学習診断機能を搭載しており、個々の理解度に応じた学習プランを提供します。
そのため、「どこが理解できていないのか?」を明確にしながら、効率よく基礎力を固めることができます。
特に、苦手分野を放置せずに、過去の学年の範囲までさかのぼって学習できるため、学校の授業についていけなくなる心配が少なくなります。
例えば、小学生のうちに数学の基本をしっかり固めておけば、中学に入ってからもスムーズに学習を進められます。
勉強効果2・短時間で「できる→わかる→応用」の流れを作ってくれる
すららの学習システムは、「問題を解いて終わり」ではなく、「理解→定着→応用」のサイクルを効率的に回せるように設計されています。
例えば、数学では「基礎問題→類似問題→応用問題」といった形で、段階的にレベルアップできるため、「なんとなく理解したつもり」ではなく、「実際に解けるようになる」までしっかりサポートしてくれます。
また、国語では「読解→要約→記述」といったステップで、単なる読み取りだけでなく、自分の考えをまとめる力も鍛えられます。
短時間でも効率よく勉強できるのは、すららの大きな強みです。
勉強効果3・中学生は主要3教科で内申点が決まるから「点数を上げたい」「定期テストで成果を出したい」という目的に直結する
中学生にとって、国語・数学・英語の3教科は、内申点に大きく影響する重要な科目です。
すららの3教科コースでは、定期テスト対策に役立つ問題演習や、理解度チェックができる小テストが充実しているため、「学校の成績を上げたい」という目的に直結しやすくなっています。
特に、苦手科目がある場合、学校の授業だけでは十分な対策ができないこともありますが、すららなら自分のペースで重点的に学習できるため、「苦手克服→得意科目へ」と変えていくことも可能です。
また、英語に関してはリスニング・スピーキング対策も充実しているため、英検や高校入試対策にも活用しやすい点がメリットです。
すらら4教科コース(国・数・英語・理科または社会)の勉強効果について紹介します
すららの4教科コースでは、国語・数学・英語に加えて、理科または社会を学習できます。
理科・社会は暗記が中心になりやすい科目ですが、すららでは「ただ覚えるだけ」ではなく、理解を深めながら知識を定着させるカリキュラムが組まれています。
特に、短時間で効率よく勉強したい人や、定期テスト対策を強化したい人にとって、この4教科コースは非常に有効です。
勉強効果1・理科・社会は、「繰り返し学習」と「確認テスト」で記憶の定着率が高まる
理科や社会は、一度学んだだけではなかなか覚えられない科目です。
そのため、すららでは「繰り返し学習」と「確認テスト」を活用しながら、知識をしっかり定着させる仕組みが整っています。
例えば、地理や歴史では、重要な用語や流れを学んだ後に、すぐに確認テストを実施することで、「理解したつもり」で終わらず、本当に覚えられているかをチェックできます。
理科では、実験のアニメーションを見ながら学ぶことで、実際の現象をイメージしやすくなり、記憶に残りやすくなるのが特徴です。
勉強効果2・ポイントを押さえた要点学習で、時間対効果がとてもいい
理科・社会は範囲が広く、覚えるべき情報が多いため、効率よく学習することが重要です。
すららでは、各単元の「要点」をしっかり押さえた学習ができるため、ダラダラと長時間勉強する必要がなく、短時間でもしっかり理解できます。
例えば、歴史なら「時代ごとの流れ」「重要な出来事の因果関係」を重点的に学習できるようになっており、理科なら「実験・観察のポイント」や「公式の使い方」を簡潔に学べる仕組みになっています。
要点を絞って学習できるため、テスト前の復習にも最適です。
勉強効果3・通常の塾や学校より、短時間で理解→テスト対策ができるところが強み
塾や学校の授業では、時間が限られているため、「すべてを完璧に理解する」ことが難しいこともあります。
しかし、すららなら自分のペースで学習できるため、短時間で効率よく理解を深めることが可能です。
特に、定期テスト前の対策では、「苦手な単元を集中して復習する」「過去の学年の内容をさかのぼって学ぶ」といった柔軟な学習ができるため、時間を有効に使えます。
短期間で成果を出したい場合や、部活や習い事で忙しい子どもにとっても、すららの4教科コースは効果的な学習方法と言えるでしょう。
すらら5教科コース(国・数・英語・理科・社会)の勉強効果について紹介します
すららの5教科コースは、主要5教科(国語・数学・英語・理科・社会)をバランスよく学べるカリキュラムになっています。
特に、中学生にとっては、定期テストや高校受験に直結するため、総合的な学力を伸ばすのに最適なコースです。
ここでは、5教科コースの勉強効果について詳しく紹介します。
勉強効果1・全教科を満遍なくカバーし、内申点・通知表UPに直結 / 特に中学生の内申点は「5教科バランス型」が必須
中学生の成績評価(通知表・内申点)は、5教科すべてのバランスが重要です。
特定の科目が得意でも、他の科目が苦手だと、総合的な評価が下がる可能性があります。
すららの5教科コースなら、すべての科目を無学年式で学べるため、「得意な教科は先取り」「苦手な教科は基礎から復習」といった学習スタイルを自由に選べます。
定期テスト対策にも活用でき、通知表の評価アップにも直結します。
勉強効果2・高校受験にも直結する実力アップ / 模試や過去問対策にも応用できる
高校受験では、5教科すべての実力が求められます。
特に、模試や過去問演習を通じて、各科目の出題傾向をつかむことが重要です。
すららでは、AIが苦手分野を分析し、必要な問題をピックアップしてくれるため、「どこを重点的に勉強すればいいのか」が明確になります。
模試や過去問対策にも応用できるため、効率よく受験勉強を進めることができます。
勉強効果3・5教科すべてAIが自動で弱点を分析し、学習計画を立ててくれるから効率的
すららの大きな特徴は、AIが学習データを分析し、個々の学習進度に合わせて最適な学習計画を立ててくれることです。
例えば、「数学の図形が苦手」「英語の長文読解が弱い」といったポイントをAIが自動で判断し、必要な復習内容を提示してくれます。
これにより、無駄な勉強を省き、短時間で効率的に学習を進められるのがメリットです。
勉強効果4・他の教材や塾より、時間あたりの学習効果は高いと感じる人が多い
塾に通う場合、移動時間や授業時間の制約があるため、学習効率が下がることもあります。
しかし、すららなら、自宅で好きな時間に学習できるため、無駄な時間を省くことができます。
また、アニメーションによる分かりやすい授業や、AIによる弱点分析を活用することで、短時間で「理解→定着→応用」へと進めるのが特徴です。
そのため、すららを利用している多くの人が、「他の教材よりも時間あたりの学習効果が高い」と感じています。
すららの5教科コースは、定期テスト・内申点対策から受験勉強まで幅広く対応できるため、「全教科をしっかり伸ばしたい」「受験に向けて総合的な学力をつけたい」と考えている方にぴったりのコースです。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららは発達障害や不登校でも安心・安全に使える理由
すららは、通常のタブレット学習とは違い、発達障害のある子どもや不登校の子どもにも配慮された設計になっています。
無学年式の学習や対話型アニメーション授業、AIによるつまずき分析など、個々の学習ペースに寄り添う仕組みが整っているため、学校の授業についていくのが難しい子どもや、人とのコミュニケーションが苦手な子どもでも、安心して学ぶことができます。
ここでは、すららが発達障害や不登校の子どもでも安心・安全に使える理由を紹介します。
安全な理由1・「本人のペースで学習できる」からプレッシャーがない
すららの無学年式学習は、学年に縛られることなく、自分のペースで学べる仕組みになっています。
学校の授業では「みんなと同じスピードで進めなければならない」というプレッシャーがありますが、すららなら、理解できるまでじっくり学習したり、得意な教科はどんどん先取りしたりすることが可能です。
そのため、「授業についていけない」「遅れを取り戻せない」といったストレスを感じずに学習できます。
学校の授業の「遅れ」や「先取り」を気にせず、マイペースに学べるから、ストレスが少ない
すららでは、学校の進度に関係なく、自分に合った学習ができます。
例えば、不登校で授業に出られなかった場合でも、学年をさかのぼって復習することが可能です。
逆に、特定の教科が得意な場合は、学年を超えて先取り学習を進めることもできます。
このように、子どもが「勉強しなきゃ…」というプレッシャーを感じることなく、マイペースで学べるのがすららの大きな魅力です。
ADHDタイプの子は「集中できる時に一気に」、ASDタイプの子は「毎日決まったペースで」、それぞれに合った使い方ができる
発達障害のある子どもは、学習の進め方に個人差があります。
すららでは、ADHDタイプ(注意欠陥多動性障害)の子どもは「集中力が高まったときに一気に進める」、ASDタイプ(自閉スペクトラム症)の子どもは「毎日決まったペースで学ぶ」といった、自分に合ったスタイルで学習ができます。
たとえば、ADHDタイプの子は「30分だけ集中して勉強する日」と「2時間続けて学習する日」を自由に調整できますし、ASDタイプの子は「毎日決まった時間に、決まった順番で学習する」といったルーティンを作りやすくなります。
このように、それぞれの特性に合わせて自由に学べる環境が整っています。
安全な理由2・「対面の緊張や不安がゼロ」だから取り組みやすい
学校や塾では、先生やクラスメイトと対面でコミュニケーションを取る機会が多く、それがプレッシャーになることもあります。
すららは、アニメーションキャラクターが授業を進めるため、対人関係のストレスを感じることなく学習できます。
人前で発言するのが苦手な子どもや、質問するのが怖いと感じる子どもでも、安心して取り組めるのがポイントです。
アニメーションのキャラが優しく教えてくれて、正解でも不正解でも感情的な反応をされることはない
すららでは、アニメーションのキャラクターが講師役を務め、優しく解説してくれます。
間違えたときに怒られたり、恥ずかしい思いをしたりすることがないため、「間違えたらどうしよう…」という不安を感じることなく、安心して学習できます。
特に、人の表情や言葉のニュアンスを気にしやすい子どもにとっては、精神的な負担が少ない学習環境となります。
人とのコミュニケーションに不安がないから安心して学ぶことができる
対面での授業では、「先生にどう質問したらいいのかわからない」「クラスメイトの視線が気になる」といった理由で、学習に集中できない子どももいます。
すららなら、人とのやりとりに不安を感じることなく、一人でじっくり学ぶことができます。
質問がある場合も、すららコーチにオンラインで相談できるため、無理に対面でやり取りする必要がありません。
こうしたサポート体制があることで、不安を感じることなく学習を続けることができます。
すららは、発達障害や不登校の子どもにとって、無理なく学習を進められる環境が整っています。
自分のペースで学べること、対人ストレスがないこと、そして安心して学べるサポートがあることが、すららが安心・安全に使える理由です。
安全な理由3・発達障害に対応した「ユニバーサルデザイン」設計
すららは、発達障害のある子どもでも無理なく学べるように、ユニバーサルデザインを取り入れた設計になっています。
ユニバーサルデザインとは、「誰にとっても使いやすい」ことを目的としたデザインの考え方です。
すららでは、視覚・聴覚・操作性に配慮し、学習のハードルをできるだけ低くする工夫がされています。
読字が苦手な子や、情報処理に時間がかかる子でもスムーズに学習を進められるため、学校の授業では理解しづらかった内容も、すららなら安心して学べます。
すららは「誰でも理解しやすく、つまずきにくい」ように作られている
すららは、単なるテキストの表示や解説ではなく、アニメーションや音声を組み合わせた「マルチモーダル学習」を採用しています。
これにより、一つの情報を「目で見て」「耳で聞いて」学ぶことができ、理解しやすくなっています。
また、学習の進行もシンプルでわかりやすく、余計な操作をせずにスムーズに進められるため、タブレット学習に不慣れな子でも迷わず学習を進めることができます。
読字障害(ディスレクシア)、言語理解に時間がかかるASDの子にも分かりやすい
発達障害の中でも、特にディスレクシア(読字障害)の子どもは、文章を読むのに時間がかかったり、正しく理解するのが難しかったりします。
すららでは、テキストだけでなく音声やアニメーションを活用して学習できるため、読字が苦手な子どもでも、聞いて学ぶことができます。
また、ASD(自閉スペクトラム症)の子どもは、言葉の意味を理解するのに時間がかかることがあります。
すららでは、具体的な例を交えながら、視覚的にわかりやすい解説が行われるため、単に言葉の説明を聞くだけの授業よりも、スムーズに理解しやすくなっています。
「視覚優位」「聴覚優位」どちらのタイプの子にもマッチしやすいのが特長
発達障害のある子どもは、情報を処理する方法に違いがあります。
「視覚優位」の子どもは、図やイラストを見ながら学ぶほうが理解しやすい傾向がありますが、「聴覚優位」の子どもは、音声での説明のほうが頭に入りやすいことがあります。
すららは、テキスト・アニメーション・音声をバランスよく組み合わせているため、どちらのタイプの子どもにも対応しやすい学習環境になっています。
例えば、算数の文章問題では、文章を読むだけでなく、イラストや図を使って問題を視覚的に理解しやすくする工夫があります。
また、理科や社会の学習では、単に用語の説明をするだけでなく、ナレーションと映像を使いながら解説するため、聴覚優位の子どもも安心して学べます。
「音声速度」を調整できる機能もあるから、「ゆっくり聞きたい」「早く進めたい」など、子どもの特性に合わせられる
すららでは、音声の再生速度を調整できる機能が搭載されています。
ASDの子どもや、情報処理に時間がかかる子どもは、通常のスピードだと理解が追いつかないことがありますが、音声をゆっくり再生することで、自分のペースで学習を進めることができます。
逆に、内容をすでに理解している子どもは、音声速度を上げてテンポよく学習を進めることも可能です。
このように、子どもの特性に合わせて柔軟に学習環境を調整できるため、「授業のスピードが合わない」と感じることなく、自分に最適なペースで学べるのがすららの大きな魅力です。
安全な理由4・間違えても怒られない・恥をかかない設計
すららは、学習に対するストレスを最小限に抑えられるように設計されています。
学校の授業や塾では、間違えたときに先生や周りの友達の反応が気になったり、「できない自分」を意識してしまうことがあります。
しかし、すららは完全に個別学習のため、他人の目を気にすることなく、自分のペースで進めることができます。
間違えても怒られることはなく、優しく導いてくれるので、安心して学習に取り組めるのが特徴です。
「否定」ではなく「納得」させてくれるから、自己肯定感が下がりにくい
すららの授業は、「間違いを指摘する」のではなく、「どうすれば正解になるのか」を優しく教えてくれるスタイルになっています。
たとえば、間違えた問題に対して「違います」と否定するのではなく、「この考え方もあるけど、こうするともっと良くなるね」と、納得感のあるフィードバックをしてくれます。
これにより、「できなかった」というネガティブな感情を抱くことなく、次に進めるのが特徴です。
特に、失敗を気にしやすい子どもや、完璧主義になりがちな子どもにとって、自己肯定感を保ちながら学習を続けられる環境はとても重要です。
学校や塾では感じがちな「恥ずかしい」「できない」といったネガティブ感情を抱きにくい
学校や塾では、先生の前やクラスメイトの前で答えを間違えてしまうと、「恥ずかしい」と感じることがあります。
この気持ちが積み重なると、「間違えるのが怖いから、発言しない」「わからない問題は飛ばしてしまう」といった消極的な学習姿勢につながることもあります。
しかし、すららなら完全に自分だけの学習環境なので、間違えることに対するプレッシャーがありません。
「間違えても大丈夫」「何度でもやり直せる」という安心感があるため、学習そのものに対して前向きな気持ちを持ち続けることができます。
安全な理由5・「ゲーム感覚」の楽しい仕組みで続けやすい
すららは、ただ勉強するだけでなく、「学習を楽しめる仕組み」がたくさん取り入れられています。
特に、アニメーションキャラクターがナビゲートすることで、無機質な学習にならず、対話しながら進めているような感覚で学べるのが特徴です。
また、クイズ形式の問題や、ステップアップしながら進むゲーム感覚の要素があるため、「もうちょっとやってみようかな」と思いやすく、自然と学習時間が伸びていきます。
アニメキャラクターがナビゲートし、クイズ形式やゲーム感覚の要素があるから「もうちょっと続けたい」と思わせる工夫がされてる
すららの学習は、アニメキャラクターがナビゲートしてくれるため、まるで先生と会話しながら勉強を進めているような感覚になります。
また、単なる問題演習ではなく、クイズ形式で出題されたり、正解すると褒めてもらえたりするなど、楽しみながら学べる仕組みになっています。
この「楽しいからもう少しやりたい」という感覚が、継続的な学習につながり、学習習慣の定着を助けてくれます。
ADHDの子は「すぐに褒められる」「すぐに結果が出る」とやる気が続きやすい傾向がある
ADHD(注意欠陥・多動性障害)の子どもは、集中が長く続かないことがありますが、「すぐにフィードバックがある」「達成感が得られる」といった要素があると、やる気を維持しやすくなります。
すららでは、問題を解くごとにすぐに正解・不正解がわかり、正解するとアニメキャラクターが褒めてくれるため、短時間でも達成感を味わえます。
また、学習が進むとステージが上がるような仕組みもあり、「あと少し頑張ろう」と思える工夫がされています。
このように、ゲーム感覚の学習ができることで、飽きっぽい子や集中が続きにくい子でも、楽しく学習を続けられるのがすららの魅力です。
安全な理由6・「すららコーチ」がいるから親子で抱え込まなくていい
発達障害や不登校の子どもが家庭学習を続ける場合、親のサポートが必要になることが多く、負担が大きくなりがちです。
しかし、すららには「すららコーチ」という専門の学習サポーターがいるため、親子で抱え込まずに学習を進めることができます。
子どもの特性や学習スタイルに合わせてサポートしてくれるため、親が細かく指導しなくても、安心して学習を継続できるのが特徴です。
ADHDやASD、学習障害の特性を理解した対応をしてくれるコーチが多い
すららコーチは、発達障害や学習障害のある子どもの特性を理解した上で、適切なアドバイスを提供してくれるため、「どうやって勉強を進めればいいのかわからない」と悩むことが少なくなります。
ADHD(注意欠陥・多動性障害)の子どもには、短時間で集中しやすい学習スケジュールを提案したり、ASD(自閉スペクトラム症)の子どもには、ルーチン化された学習方法をアドバイスしたりと、一人ひとりに合った対応をしてくれるのが魅力です。
学習のつまずきに対しても、子どものペースに合わせたフォローを行ってくれるため、「わからないまま置いていかれる」ことがありません。
コーチが学習計画を立てたり、つまずきポイントを教えてくれる
すららコーチは、学習計画を立てるサポートもしてくれるため、「どこから勉強を始めたらいいのかわからない」という悩みを解決できます。
特に、無学年式の学習では自由度が高いため、どの単元をどの順番で進めるべきか迷ってしまうことがありますが、コーチが適切な学習プランを作成し、スムーズに学習できるように調整してくれます。
また、AIによる学習診断とコーチのサポートを組み合わせることで、苦手な分野を特定し、効率よく克服できるのもポイントです。
安全な理由7・「完全オンライン」だから家で完結できる
すららは、タブレットやPCがあればすぐに学習を始められる「完全オンライン型」の教材です。
塾や学校に通う必要がないため、通学が難しい子どもや、人と直接関わることに不安を感じる子どもでも、安心して学習を進めることができます。
また、教材の準備や移動の手間がないため、親の負担も軽減されるのが大きなメリットです。
タブレット1台あればできるから、環境づくりもシンプルだし、親の負担も減る
すららの学習は、タブレットやPCがあればすぐに始められるため、特別な教材を準備する必要がありません。
従来の家庭学習では、ドリルやノートを用意し、進捗を管理する必要がありましたが、すららならすべてデジタルで完結するため、学習環境をシンプルに整えることができます。
また、親が学習の進捗を細かくチェックしなくても、すららコーチやAIが学習状況を管理してくれるため、「勉強を見てあげる時間が取れない」という悩みも軽減されます。
通学できない間も学習の「穴」を作らず、自信を持たせてあげられる
不登校の子どもにとって、学校の授業に参加できない期間が続くと、「学習の遅れ」が大きな不安要素になります。
しかし、すららなら自宅で学校の授業と同じ範囲を学ぶことができるため、学習の「穴」を作ることなく、学力を維持・向上させることが可能です。
さらに、自分のペースで学習を進められるため、「できることが増える」という成功体験を積み重ねやすく、自信を持って学び続けることができます。
オンラインで完結する学習環境は、特に「学校に戻ることが不安」「集団の中で勉強するのが苦手」という子どもにとって、安心して学べる大きなメリットになります。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの解約・退会方法について紹介します
すららは、家庭で無学年学習ができる便利なタブレット教材ですが、「学習が一段落した」「他の学習方法に切り替えたい」などの理由で解約や退会を検討する方もいるかもしれません。
すららの解約・退会手続きには、いくつかの注意点があるため、事前に確認しておくことが大切です。
特に、「解約」と「退会」は意味が異なり、それぞれの手続き内容が異なるため、違いを理解した上でスムーズに進めましょう。
すららの【退会】と【解約】は意味が異なる!それぞれの違いについて解説します
すららをやめる方法には、「解約」と「退会」の2種類があります。
この2つは似ていますが、手続きを進める前に違いを理解しておかないと、「思っていたのと違う」「データが消えてしまった」といったトラブルにつながる可能性があります。
解約と退会、それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。
すららの解約は「利用を停止すること」。毎月の支払い(利用料)を止める手続き。
すららの「解約」とは、すららの学習サービスを停止することを意味します。
解約をすると、毎月の利用料の支払いがストップし、学習コンテンツの利用ができなくなります。
しかし、解約後も会員情報は残るため、再契約すれば以前の学習データを引き継いで利用を再開することが可能です。
今後また利用する可能性がある場合は、「解約」を選ぶのがよいでしょう。
すららの退会は 「すららの会員そのものをやめること」。データも消える。
「退会」は、すららの会員情報そのものを削除する手続きです。
退会すると、学習データや利用履歴などの情報がすべて消去されるため、再開したい場合でも以前のデータを引き継ぐことはできません。
完全にすららをやめる場合にのみ、この手続きを選びましょう。
「しばらく使わないけれど、また利用するかもしれない」という場合は、退会ではなく解約を選ぶことをおすすめします。
すららの解約方法1・すららコール(サポートセンター)に電話
すららの解約手続きは、サポートセンターへの電話でのみ受け付けています。
メールやWEBからの解約申請はできないため、手続きの際には必ず電話をする必要があります。
以下が、すららの解約専用窓口「すららコール」の連絡先です。
| 【すららコール】 0120-954-510(平日10時~20時 土日祝休み) |
すららの解約はメールやWEBからは受け付けていない
最近では、多くのオンラインサービスがメールやWEB上で解約できる仕組みを導入していますが、すららの解約は電話でのみ受け付けています。
これは、解約時に登録情報の確認や、手続きに関する説明を行うためです。
電話がつながりにくい場合もあるため、時間に余裕を持って連絡することをおすすめします。
すららの解約方法2・電話で本人確認/登録者氏名・ID・電話番号など
すららの解約手続きでは、電話での本人確認が必要になります。
解約を希望する際には、以下の情報を準備しておくとスムーズに手続きを進めることができます。
– 登録者氏名(契約時に登録した名前)
– すららの会員ID(ログイン時に使用するID)
– 登録している電話番号
オペレーターに伝えた後、解約の手続きを進めてもらうことになります。
なお、手続きの途中で確認事項がある場合もあるため、電話ができる環境で落ち着いて連絡することをおすすめします。
すららの解約方法3・解約希望日を伝える/日割り計算はされません
解約の際には、「いつまで利用するのか」を伝える必要があります。
ただし、すららの解約では、利用料の日割り計算は行われません。
つまり、月の途中で解約をしても、月末までの利用料金は発生するため、解約を検討する際は、契約更新日のタイミングを確認しておくことが重要です。
例えば、契約更新日が毎月1日の場合、月末まで利用した後に解約を申し込むことで、無駄な料金を支払わずに済みます。
すららの解約・退会を検討している場合は、まず「解約」と「退会」の違いを理解することが重要です。
今後再利用する可能性がある場合は「解約」、完全にすららをやめる場合は「退会」を選びましょう。
解約の手続きは電話でのみ受け付けており、事前に登録情報を用意しておくとスムーズに進められます。
また、解約を申し込むタイミングによっては、無駄な料金を支払うことになるため、契約更新日をしっかり確認しておくことが大切です。
すららをやめる際には、今回紹介した手続きを参考に、スムーズに解約・退会を進めてください。
すららの退会方法について/解約手続き完了後に退会依頼をする
すららを完全にやめたい場合は、「解約」だけでなく「退会」の手続きが必要になります。
ただし、すららは解約手続きをした時点で料金の支払いが停止するため、必ずしも退会手続きを行う必要はありません。
ここでは、すららの退会手続きについて詳しく解説します。
すらら解約の電話時に退会希望の旨を伝える
すららの退会を希望する場合は、解約の手続きと同時に「退会したい」旨を伝える必要があります。
解約手続きを進める際に、オペレーターに「退会も希望します」と申し出ることで、解約と退会の両方の処理をしてもらうことができます。
退会すると、すららの学習履歴や登録情報がすべて削除されるため、今後すららを再利用したい場合でも、データを引き継ぐことはできません。
完全にすららをやめる場合のみ、退会手続きを行うようにしましょう。
すらら解約後に退会をしなくても全く問題はありません(料金の支払いは停止します)
すららの退会手続きをしなくても、解約を完了すれば、毎月の料金の支払いは自動的に停止されます。
そのため、「また使うかもしれない」「しばらく様子を見たい」という場合は、解約のみを行い、退会はせずにおくのがおすすめです。
解約をしても会員情報は保持されるため、再契約すれば以前の学習データを引き継ぐことができます。
もし、完全にすららを辞めることを決めた場合は、解約手続きが完了した後、退会手続きを申し込むようにしましょう。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの効果的な使い方について紹介します
すららは、自宅で効率よく学習できる家庭用タブレット教材ですが、「どのように活用すれば効果的なの?」と悩む方もいるかもしれません。
特に、小学生の場合は、学習習慣をつけることや、楽しく続ける工夫が必要になります。
ここでは、小学生がすららを最大限活用するための効果的な使い方を紹介します。
【小学生】すららの効果的な使い方について紹介します
小学生がすららを使う際には、「短時間×頻度」「楽しさをプラス」「苦手克服」の3つのポイントを意識すると、効果的に学習を進めることができます。
特に、低学年のうちは親のサポートが重要になるため、一緒に取り組む姿勢を大切にしましょう。
使い方1・「短時間×頻度」でリズムを作る/1回20〜30分を目安に、毎日少しずつ続ける
小学生の学習では、「長時間まとめて勉強する」よりも、「短時間で毎日続ける」ほうが効果的です。
すららを活用する際は、1回20〜30分程度を目安に学習するのがおすすめです。
例えば、朝の10分+放課後の20分といったように、短い時間を習慣化すると、無理なく続けることができます。
集中力が続かない子どもには、タイマーを使って「20分だけ頑張ろう」と区切ると、学習へのハードルを下げることができます。
毎日コツコツ続けることで、学習のリズムができ、自然と成績向上につながります。
使い方2・「ごほうび制度」を活用する/1ユニット終わったらシールを貼るとか、小さな達成感を演出すると、やる気が続く
小学生は、「達成感」を感じることでモチベーションが上がりやすい傾向があります。
そのため、すららの学習を進める際には、ゲーム感覚で「ごほうび制度」を取り入れるのがおすすめです。
例えば、「1ユニット(1つの学習ステップ)を終えたらシールを貼る」「3日続けたら好きなお菓子を選べる」「1週間続けたらちょっとしたご褒美を用意する」といったルールを作ると、子どもも楽しみながら学習に取り組めます。
「もうちょっと頑張ろう!」と思える工夫をすることで、学習習慣が自然と身につきます。
使い方3・親も一緒に楽しむ姿勢を/とくに低学年は、親が「一緒にやろう!」と言うと素直に取り組むことが多い
特に低学年のうちは、親が「勉強しなさい!」と言うよりも、「一緒にやってみよう!」と声をかけるほうが、子どもは素直に学習に取り組みやすくなります。
すららのアニメーション授業は、親が見ても楽しめる内容なので、「どんな内容なのか一緒に見てみよう」と誘うと、自然と学習の習慣がつきやすくなります。
また、親が隣で「今の問題、面白かったね!」「すごい!よく分かったね!」と声をかけることで、子どもは「勉強が楽しい」と感じやすくなります。
すららは一人でも学べる教材ですが、低学年のうちは親が適度に関わることで、学習のモチベーションを維持しやすくなります。
使い方4・苦手克服から入るのがおすすめ/好きな科目ばかりやると偏るから、すららのAI診断で弱点を把握して、そこから攻略する
すららは、無学年式で自由に学習できるため、子どもが好きな科目ばかり進めてしまうこともあります。
しかし、苦手科目をそのままにしておくと、学年が上がるにつれて苦手が積み重なり、学習の負担が大きくなってしまいます。
そこでおすすめなのが、すららのAI診断を活用して、苦手な単元を把握し、そこから学習を始める方法です。
例えば、算数の計算ミスが多い場合は「小学校低学年の基礎に戻って復習する」、国語の読解が苦手なら「文章の読み取り練習を重点的に行う」といった学習方法を取ることができます。
AIが自動で弱点を分析してくれるため、親が細かくチェックしなくても、効率的に学習を進めることが可能です。
すららを効果的に活用するには、「短時間×頻度で続ける」「ごほうびを活用してやる気を引き出す」「親も一緒に楽しむ」「苦手克服を優先する」という4つのポイントを意識することが大切です。
楽しく学習を続けられるように、子どもに合った使い方を工夫してみましょう。
【中学生】すららの効果的な使い方について紹介します
中学生になると、定期テストや部活、高校受験など、勉強の負担が大きくなります。
そのため、「すらら」を活用して、効率よく学習を進めることが重要になります。
すららは、無学年式のため、予習・復習のどちらにも対応しやすく、AIを活用した苦手克服も可能です。
ここでは、中学生がすららを最大限に活用するための効果的な使い方を紹介します。
使い方1・「定期テスト対策」に直結させる/単元ごとにまとめテストがあるから、テスト範囲を逆算して、今どこをやるべきか計画を立てる
すららでは、単元ごとにまとめテストが用意されているため、定期テスト対策として活用するのに最適です。
テスト勉強を始める際には、まず「テスト範囲を確認する」ことが重要です。
その上で、すららのカリキュラムを活用し、どの単元を重点的に学習すべきか逆算して計画を立てると、効率的に対策を進めることができます。
また、まとめテストを繰り返し解くことで、試験本番に向けた実践的な演習ができ、得点アップにつながります。
定期テスト直前は、新しい単元に手をつけるのではなく、すららの復習機能を活用して、苦手を重点的に学習するとよいでしょう。
使い方2・部活後の「夜学習」を習慣に/寝る前の「タブレット学習ルーティン」を決めると、ペースが乱れない
中学生は部活が忙しく、帰宅後は疲れて勉強のモチベーションが下がりがちです。
そこでおすすめなのが、「夜学習」の習慣化です。
例えば、「寝る前の30分は必ずすららをやる」とルールを決めることで、ペースを維持しやすくなります。
タブレット学習は、机に向かって重たい参考書を開く必要がないため、部活後の疲れた状態でも取り組みやすいのがメリットです。
また、寝る前の学習は記憶の定着を助ける効果があるため、英単語の暗記や数学の公式の理解など、短時間でできる学習を習慣化すると、無理なく成績アップにつながります。
使い方3・「すららコーチ」をフル活用/学習計画のアドバイスやつまずきのサポートをしてくれる
中学生になると、勉強の範囲が広がり、どこから手をつければいいのかわからなくなることがあります。
そんなときに活用したいのが「すららコーチ」です。
すららコーチは、学習計画の作成や、苦手分野のアドバイスをしてくれるため、「何をどう勉強すればいいのか」を具体的にサポートしてくれます。
例えば、「数学が苦手だけど、どこから復習すればいいのかわからない」といった場合、すららコーチに相談すれば、AI分析をもとに適切な学習方法を提案してもらえます。
受験対策や定期テストのスケジュール管理にも役立つため、積極的に活用するのがおすすめです。
使い方4・「復習と予習」をバランスよく/英語や数学の文法・公式の理解は予習でやると授業が楽しくなる
中学生の学習では、「復習」だけでなく「予習」も重要です。
特に英語や数学は、事前に文法や公式を理解しておくことで、学校の授業がスムーズに進みます。
すららの授業は、アニメーションを使ったわかりやすい解説が特徴なので、予習に最適です。
たとえば、次の授業で習う単元をすららで先に学んでおくと、授業中に「すでに知っている内容」として理解が深まり、成績向上につながります。
また、授業で理解しきれなかった部分をすららで復習することで、知識の定着をより強固なものにすることができます。
「予習→学校の授業→復習」というサイクルを作ることで、効率よく学習を進めることができます。
中学生がすららを効果的に使うには、「定期テスト対策に活用」「夜学習の習慣化」「すららコーチの活用」「予習と復習のバランス」の4つのポイントを意識することが重要です。
忙しい中でも、計画的に学習を進めることで、無理なく成績アップにつなげることができます。
【高校生】すららの効果的な使い方について紹介します
高校生になると、勉強の難易度が上がり、授業についていくのが大変になることがあります。
また、模試や共通テスト対策、高校卒業後の進路を考える時期でもあるため、効率よく学習することが求められます。
すららは、基礎学力の定着や自分のペースでの学習に適しているため、高校生にとっても効果的な学習ツールとなります。
ここでは、すららを高校生が最大限に活用する方法を紹介します。
使い方1・「苦手克服」×「得意分野の強化」を並行する/つまずいてるところは基礎から復習し、得意分野は応用問題に挑戦する
高校の勉強では、「苦手を放置すると後で取り返しがつかなくなる」ことがよくあります。
そのため、すららを活用して「苦手克服」と「得意分野の強化」を並行して進めることが大切です。
苦手な分野については、すららの無学年式学習を活かし、中学レベルまでさかのぼって基礎から復習すると効果的です。
特に数学や英語は、基本が理解できていないと応用問題が解けなくなるため、早めに復習しておくとよいでしょう。
一方で、得意な分野は、すららの演習問題や応用問題に挑戦し、さらなるレベルアップを目指します。
「苦手を克服しつつ、得意分野を伸ばす」ことで、全体的な学力をバランスよく向上させることができます。
使い方2・学校の授業が合わない場合は、すららで自分に合うペースで進める
高校の授業は、進度が速く、内容が難しいため、「授業についていけない」「先生の説明がわかりにくい」と感じることもあるかもしれません。
そんなときは、すららを使って「自分のペースで学ぶ」ことで、理解を深めることができます。
すららは、アニメーションによる解説があり、学校の授業よりもわかりやすく学習できることが多いのが特徴です。
特に、数学や英語など、基礎をしっかり固めることが重要な教科では、すららを使って予習・復習をすることで、学校の授業が理解しやすくなります。
また、授業の進度が速すぎる場合は、すららでゆっくり学び直し、逆に「授業が簡単すぎる」と感じる場合は、先取り学習をすることで、より効率的に学習を進めることができます。
使い方3・模試や共通テスト対策に連動/すららは基礎力の定着にはかなり強い
高校生にとって、模試や共通テストの対策は欠かせません。
すららは、特に「基礎力の定着」に強い教材のため、模試や共通テスト対策の土台作りに最適です。
まず、模試や共通テストで出題される基本的な知識を、すららのカリキュラムで確実に理解しておくことが重要です。
共通テストでは、知識を活用する問題が多いため、すららの解説をしっかり確認しながら学習すると、問題の理解が深まります。
また、模試の結果をもとに、「どの分野が苦手なのか」を分析し、すららで重点的に復習するのも効果的です。
例えば、「英語のリーディングが苦手なら、すららの英文読解講座を活用する」「数学の関数が弱いなら、基礎からやり直す」といったように、すららを使って弱点を克服していくと、模試の点数アップにつながります。
使い方4・学習時間を「見える化」する/学習時間や達成度がグラフで表示される
高校生は、大学受験や進路選択に向けて、どれだけ勉強したかを意識することが大切です。
すららでは、学習時間や達成度がグラフで表示されるため、「どれだけ勉強したか」を客観的に把握しやすくなります。
学習時間を可視化することで、「今月は〇時間勉強できた」「先月よりも学習時間が増えた」といったように、モチベーションを維持することができます。
また、毎日の学習目標を設定し、「1日1時間はすららをやる」など、具体的な目標を持つことで、計画的に学習を進められます。
さらに、すららの学習記録を振り返ることで、「どの分野をどれだけ勉強したか」が分かるため、得意・苦手のバランスを考えながら学習を進めることもできます。
高校生がすららを効果的に活用するためには、「苦手克服と得意分野の強化を並行する」「自分に合ったペースで学習する」「模試や共通テスト対策に活用する」「学習時間を可視化してモチベーションを維持する」の4つのポイントが重要です。
すららを上手に活用し、基礎力をしっかり固めながら、効率よく学習を進めていきましょう。
【不登校】すららの効果的な使い方について紹介します
不登校の子どもにとって、「学習の遅れが気になる」「生活リズムが崩れがち」「一人で勉強するのが不安」といった悩みを抱えることが多くあります。
すららは、無学年式の学習システムを活用しながら、自宅でも安心して学習を続けられるように設計されているため、不登校の子どもにとっても大きなサポートとなります。
ここでは、不登校の子どもがすららを効果的に活用する方法について紹介します。
使い方1・「生活リズム作り」に役立てる/朝起きる→学習→休憩…の「ミニ時間割」を作って生活リズムを整えられる
不登校になると、生活リズムが乱れやすく、夜更かしや昼夜逆転の状態になってしまうことも少なくありません。
すららを活用することで、学習の時間を決め、規則正しい生活習慣を作ることができます。
例えば、「朝10時に起きる→11時から30分学習→昼食→午後にまた30分学習→夕方は自由時間」といった「ミニ時間割」を作ることで、無理なく生活リズムを整えることができます。
毎日決まった時間に学習をすることで、「勉強の習慣化」と「生活リズムの安定」を両立させることができます。
使い方2・「一人でも安心してできる環境」を整える/自分のペースで、周りを気にせず学べるのがすららの強み
学校では、クラスメイトと一緒に勉強することが当たり前ですが、不登校の子どもにとっては、対人関係のストレスが学習の妨げになることもあります。
すららは、完全オンラインの学習システムのため、誰にも干渉されずに自分のペースで学習を進めることができます。
例えば、「学校の授業の進度を気にせず、自分が理解できる範囲から始める」「苦手なところは何度でも繰り返し学ぶ」といった学習方法が可能です。
周囲の目を気にせず、自宅でリラックスしながら学習できる環境を整えることで、勉強に対するハードルを下げることができます。
使い方3・「成功体験」を増やして自信を回復/すららの「ほめ機能」を活用する
不登校の子どもは、「学校に行けない自分」「勉強についていけないかもしれない」という不安から、自信を失ってしまうことがあります。
すららには、学習の達成感を得られるような「ほめ機能」があり、小さな成功体験を積み重ねることができます。
例えば、「問題を解くたびにキャラクターが励ましてくれる」「目標を達成すると達成度が表示される」といった機能を活用することで、勉強に対する前向きな気持ちを育てることができます。
すららを通じて、「できた!」という体験を増やし、自信を少しずつ取り戻していくことが大切です。
使い方4・コーチングの活用で「孤立感」を減らす/すららコーチに相談すると、親とは違う「第三者の声」がもらえるので、気持ちの負担が和らぐ
不登校の子どもは、家で過ごす時間が増えるため、どうしても「孤立感」を感じやすくなります。
そのようなときに役立つのが、「すららコーチ」の存在です。
すららコーチは、学習の進め方のアドバイスをしてくれるだけでなく、子ども一人ひとりの状況に寄り添い、励ましてくれる役割も担っています。
親以外の「第三者」として関わることで、勉強だけでなく、気持ちの面でもサポートを受けることができます。
例えば、「勉強の進め方がわからない」「どこから手をつければいいかわからない」といった悩みがあれば、すららコーチに相談することで、安心して学習を続けられるようになります。
不登校の子どもがすららを活用する際は、「生活リズムを整える」「一人でも安心して勉強できる環境を作る」「小さな成功体験を増やして自信を回復する」「すららコーチを活用して孤立感を減らす」といったポイントを意識することが大切です。
すららを上手に活用しながら、自分のペースで学習を続けることで、少しずつ前向きな気持ちを取り戻していきましょう。

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららを実際に利用したユーザーの評判を紹介します
良い口コミ1・うちの子は、元々タブレットが好きで、ゲーム感覚で学べるところがハマったみたいです。アニメのキャラが優しく教えてくれるので、塾に行くよりも緊張しないし、自分のペースでできるのが良いみたい
良い口コミ2・ADHD気味で集中力が長続きしない子でも、すららはアニメーションやイラストで説明してくれるので理解しやすいです
良い口コミ3・学校に通えない期間が長く、勉強にブランクがありましたが、すららなら自分のレベルに合わせて無理なく進められました。先生の顔を見ずに自分だけのペースで学べるので、安心感があります
良い口コミ4・塾に通う時間が取れなかったけど、すららは家でスキマ時間にできるから便利!部活が忙しくても、夜に少しずつ進めていけるし、テスト対策にも使えるのがいい
良い口コミ5・発達に凸凹があって、書くことが苦手な子ですが、すららはタブレット操作で進められるので、嫌がらずに学習ができています
悪い口コミ1・タブレットで勝手に学んでくれると思っていたけど、低学年の子は一人で進めるのが難しいこともあり、結局そばで見守ることに…。もう少し親が楽できる設計だったらよかったかな
悪い口コミ2・初めは楽しく続けられていたのですが、不登校の子だと一度やる気が下がると放置してしまう…。サポートメールや先生からのアドバイスは来るけど、やっぱり一人だと限界を感じることもあります
悪い口コミ3・高校生用のコースを受講していますが、基礎に時間をかけすぎる印象です。進学校に通っていると、物足りなさを感じるかもしれません
悪い口コミ4・アニメーションで楽しく学べるのはいいけれど、うちの子は飽きるのも早くて…。もう少し、変化に富んだコンテンツがあると良いですね
悪い口コミ5・通塾よりは安いですが、長期間利用を考えるとそれなりに負担感があります。特に兄弟で同時に使う場合は、一人ずつの契約が必要なので、コストはやっぱりかさみます

【すらら】はうざい!?家庭用タブレット教材すららの会社概要を紹介します
| 運営会社 | 株式会社すららネット |
| 創業 | 2008(平成20)年8月29日 |
| 本社住所 | 〒101-0047
東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田7階 |
| 従業員数 | 正社員88人、契約社員5人 |
| 資本金 | 298,370千円 |
| 代表取締役 | 湯野川 孝彦 |
| すらら公式サイト | https://surala.co.jp/ |
| すららの講座一覧 | ・3教科(国・数・英)コース
・4教科(国・数・理・社)コース ・5教科(国・数・理・社)コース |
参照: 会社概要 (すらら公式サイト)

【すらら】はうざい!?についてのよくある質問
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
多くの人が「すららはうざい」という口コミを目にすることがありますが、その背景にはいくつかの理由が考えられます。
一つ目は、すららが自身の利便性を高める一方で、個人情報を求めることでユーザーに不安を抱かせる点です。
二つ目は、すららが繰り返し同じ情報を求めることで、使い勝手が悪いと感じるユーザーがいることです。
三つ目は、広告やプッシュ通知が過剰であると感じるユーザーがいることも挙げられます。
これらの理由から、「すららはうざい」という口コミがあるのかもしれません。
そのため、ユーザーの利便性やプライバシーへの配慮を念頭に置きつつ、サービスの改善に努めることが重要です。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららでは、幅広いニーズにお応えするため、発達障害コースの料金プランをご用意しております。
当施設の発達障害コースは、患者様一人一人の症状やニーズに合わせたカスタマイズされたサービスを提供しており、その料金は個々の状況によって異なります。
初回のカウンセリングを通じて、患者様の現状を把握し、最適なプランをご提案いたします。
料金についての詳細は、お問い合わせいただくか、ウェブサイトをご覧ください。
すららでは、皆さまが安心してサービスを受けられるよう努めておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
関連ページ: すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
すららのタブレット学習は、不登校の子供たちにも利用されることがありますが、それによって出席扱いになるかどうかについて疑問があります。
不登校の子供たちにとって、通常の学校への出席が難しい場合、すららのタブレット学習は貴重な選択肢となるかもしれません。
しかし、出席扱いに関しては、教育機関や地域のポリシーによって異なる可能性があります。
教育機関がすららのタブレット学習を出席として認めるかどうかは、その学校や自治体の方針によります。
一部の学校や地域では、オンライン学習や自宅での学習も出席として認められる場合があります。
ただし、通学義務や所定の出席日数の規定がある場合、すららの学習だけで不登校の状態から完全に出席扱いになるかは確約されていません。
不登校の背景や状況によっては、学校との調整やカウンセリングの必要性が生じる可能性があります。
すららのタブレット学習を利用する際には、関係機関や学校との十分なコミュニケーションが欠かせません。
不登校の子供たちにとって、学習環境を整えるためのサポートが重要ですので、適切な対応が求められるでしょう。
関連ページ: すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららへようこそ!すららでは、お得なキャンペーンコードを活用してさまざまな学習教材を手に入れることができます。
キャンペーンコードの使い方についてご案内いたします。
まず、すららのウェブサイトにアクセスし、ログインを行ってください。
その後、希望する教材を選択してカートに入れます。
決済画面に進む際、そこにある「キャンペーンコードを入力」欄に、お持ちのキャンペーンコードを入力してください。
次に、適用ボタンを押すことで、キャンペーンコードが適用され、割引や特典が反映されます。
最後に、お支払い方法を選択して決済を完了させれば、お得な取引を享受することができます。
ぜひ、すららのキャンペーンコードをうまく活用して、充実した学習体験をお楽しみください。
関連ページ: すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
ご利用いただき、誠にありがとうございます。
退会手続きに関しては、以下のステップをご案内いたします。
まず、ログインされた状態でマイアカウントにアクセスしてください。
そこから、退会処理を行うためのボタンが設置されておりますので、クリックしてください。
必要事項を入力いただき、手続きを完了してください。
なお、退会処理が完了した後は、アカウントへのアクセスができなくなりますので、ご注意ください。
退会手続きに関する詳細や不明点がございましたら、お気軽にカスタマーサポートまでお問い合わせください。
改めてご利用いただき、誠にありがとうございました。
関連ページ: すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららでは、基本的に入会金と毎月の受講料以外に追加で料金が発生することはほとんどありません。
学習に必要なコンテンツはすべて受講料に含まれており、追加教材を購入する必要もありません。
ただし、利用するためにはタブレットやパソコン、インターネット環境が必要になるため、これらの機器を持っていない場合は別途用意する必要があります。
また、すららを利用するにあたって専用の教材やプリントを印刷することは推奨されていませんが、家庭でノートを使って復習したい場合は、ノートや筆記用具などの準備が必要になることもあります。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららは、1つの契約で兄弟や家族と一緒に利用することが可能です。
他のタブレット学習教材では、1人ずつ契約が必要な場合が多いですが、すららでは「兄弟で共有できる」という特徴があります。
ただし、学習履歴や進捗状況は1つのアカウントで管理されるため、それぞれが個別に進めたい場合は、追加アカウントを契約する必要がある場合があります。
兄弟で同じアカウントを使う場合、学習の進行状況が混ざってしまうこともあるため、どのように利用するかを事前に決めておくとよいでしょう。
すららの小学生コースには英語はありますか?
すららの小学生コースには英語の学習も含まれています。
英語は、リスニング・リーディング・スピーキングといった「英語の3技能」をバランスよく学べるカリキュラムになっており、特に英語に苦手意識を持つ子どもでも無理なく取り組めるよう工夫されています。
ネイティブの発音を聞きながら学習できるリスニング機能や、発音チェック機能もあり、英検対策にも役立ちます。
また、すららの英語はアニメーションを活用した授業形式になっているため、単なる暗記ではなく、楽しみながら英語を身につけることができます。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららのコーチ(すららコーチ)は、学習の進め方やモチベーション維持のサポートをしてくれる専門スタッフです。
主に以下のようなサポートを受けることができます。
1. **学習計画の作成と調整**
子ども一人ひとりの状況に合わせて、無理なく進められる学習計画を提案してくれます。
学習ペースが乱れがちな場合も、コーチが適切なアドバイスをくれるため、計画的に学習を進めることができます。
2. **つまずきポイントの分析とアドバイス**
AIによる診断機能を活用し、子どもがどこでつまずいているのかを把握し、適切な学習方法を提案してくれます。
特に苦手科目の克服に役立ちます。
3. **保護者へのフィードバック**
学習の進捗状況について、定期的に保護者へフィードバックがあります。
これにより、親が細かく学習状況を管理しなくても、子どもがしっかり学習を続けているかを把握することができます。
4. **モチベーションの維持サポート**
「学習が続かない」「やる気が出ない」といった悩みに対して、適切な声かけや励ましを行い、学習習慣の定着をサポートしてくれます。
親が直接言うよりも、第三者からのアドバイスのほうが効果的なことも多いため、子どもが学習に前向きになれるよう導いてくれます。
すららコーチのサポートを活用することで、子どもが無理なく学習を続けられる環境を作ることができるため、「勉強の進め方がわからない」「自分で計画を立てるのが苦手」という子どもにとって、大きな助けとなります。
参照: よくある質問 (すらら公式サイト)

【すらら】はうざい!?他の家庭用タブレット教材と比較しました
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較まとめ
今回は【すらら】というタブレット教材について、料金や最悪の噂についてまとめてきました。
さまざまな口コミや比較を通じて、その特徴や評判について詳しくご紹介しました。
【すらら】は、その便利さや使いやすさから多くの方に支持されていますが、一方で料金面や一部のユーザーからの批判もあることがわかりました。
しかし、教材選びにおいては、個々のニーズや環境に合った最適な選択が重要です。
【すらら】が他の教材よりも優れている点や改善が必要な点を把握し、自身やお子様にとって最適な教材かどうか検討することが大切です。
口コミや評判を参考にしつつ、冷静な判断をすることで、満足度の高い教材選びが可能となるでしょう。
教育においては、子どもたちの成長や学びをサポートする教材選びは非常に重要です。
【すらら】を含む様々な教材やサービスを比較検討する際には、情報を正しく理解し、将来に向けての教育環境を整えるための一助として活用していただければ幸いです。
【すらら】を含むタブレット教材の口コミや比較情報を通じて、皆さまの教育環境の向上にお役立ていただければ幸いです。

