すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について
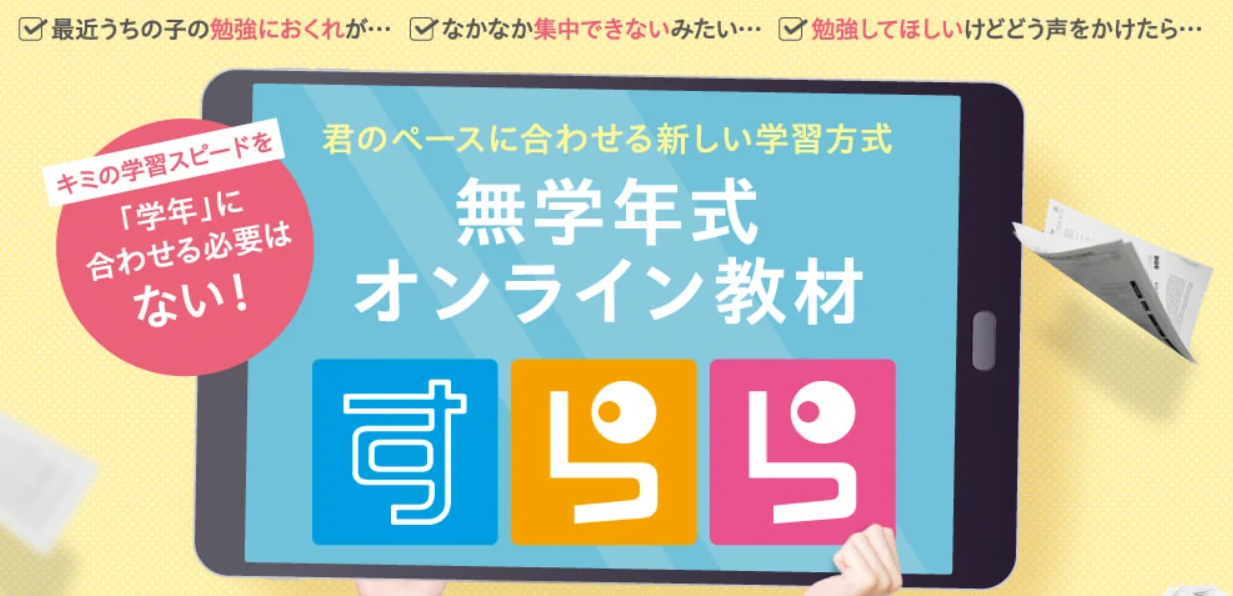
すららは、不登校の子供たちにとって学習の継続をサポートするオンライン教材です。
不登校になると、どうしても「学習の遅れが心配」「学校に行かないと出席日数が足りなくなるのでは」といった不安を感じることが多いですが、すららを活用することで学校の「出席扱い」として認められるケースがあります。
これは、すららが単なるオンライン学習ではなく、学習記録の証明や計画的な学習サポートを提供しているためです。
この記事では、すららが不登校でも出席扱いとして認められる理由について詳しく解説します。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららは、学習の質が高く、学習履歴を正確に記録する仕組みが整っています。
文部科学省のガイドラインでは、不登校の子供がオンライン学習を活用する場合、「適切な学習状況の記録と学校への報告」が求められています。
すららでは、これらの要件を満たすために、客観的な学習データを記録し、学校側に提出できるようにしているため、出席扱いとして認められやすくなっています。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららでは、子供がどの科目をどれくらい学習したか、進捗状況や理解度の変化などを詳細に記録するシステムが用意されています。
これにより、学習の証明として学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出することができます。
学校が出席扱いと認めるためには、「どの程度学習しているのか」「学校の教育課程に沿った学習ができているのか」といった点が重要視されますが、すららはこれらを具体的なデータとして示すことができるため、学校側も出席扱いの判断がしやすくなります。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
すららの学習記録は、自動的に蓄積されるため、保護者が手作業で学習状況を管理する必要がありません。
不登校の子供の学習を家庭でサポートする際、親が「学習の進捗を細かく記録し、学校に報告する」という作業は大きな負担になります。
しかし、すららではシステムが自動で学習記録を管理し、必要なレポートを作成してくれるため、保護者の負担を減らしながら、学校側にも正確な学習状況を伝えることができます。
これにより、学校側も「しっかり学習が進んでいる」という安心材料を得ることができ、出席扱いとして認めやすくなるのです。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
不登校の子供にとって重要なのは、「学習を継続する仕組みがあるかどうか」です。
すららは、単にオンライン教材を提供するだけでなく、個別の学習計画を作成し、継続的な学習サポートを行うことで、学校に通わなくても学習の進捗を確保できる環境を整えています。
特に「計画性」と「継続性」がセットでアピールできる点が、出席扱いとして認められやすい理由のひとつです。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
すららには「すららコーチ」と呼ばれる学習サポートの専門家がいます。
すららコーチは、子供の学習状況を確認しながら、個別の学習計画を作成してくれます。
学習の「計画性」があることで、学校側に「自己流で学習しているのではなく、しっかりと計画的に勉強を進めている」ことを示すことができます。
また、コーチのサポートを受けながら学習を続けることで、「継続性」が確保されるため、学校側も「途中で学習が止まってしまうのではなく、継続して学べる環境がある」と判断しやすくなります。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
学習計画を立てるだけではなく、すららコーチは定期的に子供の学習進捗を確認し、必要に応じて計画を調整してくれます。
不登校の子供は、学習へのモチベーションが下がりやすかったり、ペースをうまくコントロールできなかったりすることがあります。
そうした場合でも、すららコーチが適切なサポートを提供しながら、無理なく学習を続けられるように調整してくれます。
これにより、「自己管理が苦手な子供でも、きちんと学習が続けられる環境が整っている」と学校側にアピールすることができます。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
不登校になると、「学校の授業に遅れてしまうのでは」という心配がつきものです。
しかし、すららは無学年式のカリキュラムを採用しているため、学年にとらわれず、自分の理解度に合わせて学習を進めることができます。
例えば、「得意な科目はどんどん先に進む」「苦手な分野は戻って復習する」といった柔軟な学習が可能です。
このように、個々の学習ペースに応じて進められるため、「学校の授業についていけなくなる心配が少ない」という点が、出席扱いとして認められる要因のひとつになっています。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
すららが不登校の子供の出席扱いとして認められやすい理由のひとつに、「家庭・学校・すららの三者で連携が取れる」という点があります。
不登校の子供の学習を学校側に理解してもらうためには、家庭だけでなく、学校とのスムーズな情報共有が重要になります。
すららは、学習の証明や必要書類の準備など、学校との連携をサポートする仕組みが整っているため、家庭だけで対応するよりも、よりスムーズに出席扱いの申請を進めることができます。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
学校で出席扱いとして認められるためには、学習状況を示す書類の提出が求められることがあります。
すららでは、そうした書類の準備方法について詳しく案内をしてくれるため、「何を準備すればいいのかわからない」という保護者の不安を軽減できます。
具体的には、どのような書類が必要なのか、どのタイミングで提出すべきなのかなど、具体的な手順を示してくれるため、学校とのやりとりがスムーズに進められます。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
出席扱いとして認められるためには、「どの科目をどれだけ学習したか」といった具体的な学習内容を示すレポートが必要になります。
すららでは、専任コーチが学習レポートのフォーマットを用意し、適切な形で提出できるようフォローしてくれます。
これにより、保護者が一からレポートを作成する手間が省けるだけでなく、学校側にとっても「客観的な学習記録」として受け取りやすい形になります。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
不登校の子供が出席扱いとして認められるかどうかは、学校側の判断による部分が大きいです。
そのため、担任や校長とのスムーズな連携が重要になります。
すららでは、学校側と連絡を取りやすくするためのアドバイスやサポートを提供しており、どのように学校へ相談すればよいのか、どのように話を進めれば理解してもらいやすいのか、といった具体的なアプローチを示してくれます。
これにより、学校との交渉がスムーズになり、出席扱いとして認められる可能性が高まります。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、単なるオンライン学習教材ではなく、文部科学省が推奨する「不登校対応教材」としての実績があります。
全国の教育委員会や学校と連携し、不登校の子供たちが自宅で学習を継続できるように支援してきた実績があるため、学校側も「信頼できる教材」として受け入れやすくなっています。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららは、これまでに全国のさまざまな教育委員会や学校と連携し、不登校の子供たちの学習支援を行ってきました。
実際に、すららを活用して出席扱いになった事例も多数あるため、「すららを利用することで学校のカリキュラムに沿った学習ができる」という認識が広がっています。
こうした実績があることで、学校側もすららを信頼しやすくなり、出席扱いとして認められるケースが増えています。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
すららは、文部科学省の方針に基づき、不登校支援教材として多くの学校で導入されています。
公式に「不登校支援教材」としての利用実績があるため、「すららを活用すれば、学校に準ずる学習環境が整う」と認められやすくなっています。
特に、学校の授業と同じ学習指導要領に沿って学べる点が評価されており、学校側が出席扱いとして判断しやすい要因のひとつとなっています。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
学校が出席扱いを判断する際、「その学習環境が学校の授業と同等であるかどうか」が重要なポイントになります。
すららは、学習指導要領に沿ったカリキュラムを採用しており、さらに、学習の進捗や評価をシステム的に管理できるため、「学校に準ずる学習環境」として認められやすくなっています。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららの教材は、文部科学省の学習指導要領に基づいて作られています。
そのため、学校で学ぶ内容と大きく異なることはなく、「学校に行かなくても、同じレベルの学習ができる」ことが証明しやすくなっています。
不登校の子供が家庭で自己学習を行う場合、学校のカリキュラムとズレがあると「学習の質が担保されていない」と判断されることがありますが、すららなら、その心配がありません。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
学校の授業では、教師が生徒の学習状況を把握し、必要に応じてフィードバックを行います。
すららでも、学習の進捗を記録し、必要に応じてフィードバックを受けることができるため、「学習の質」が担保されています。
また、すららコーチが学習の進み具合を確認しながらサポートしてくれるため、「ただ自習をしているだけ」ではなく、「適切な指導のもとで学習を進めている」という形が整っています。
このような仕組みがあることで、学校側も「すららの学習環境は学校に準ずる」と判断しやすくなり、出席扱いとして認められやすくなるのです。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について
学校に通えない期間が続いても、オンライン学習を活用することで「出席扱い」として認められる制度があります。
すららを活用して学習を続けることで、一定の条件を満たせば、学校側が出席扱いとして判断する可能性があります。
しかし、申請の流れは学校や自治体によって異なるため、事前にしっかりと確認することが大切です。
ここでは、出席扱いの制度を申請するための具体的な方法について解説します。
申請方法1・担任・学校に相談する
出席扱いとして認められるためには、まず学校との連携が欠かせません。
担任の先生や学校側と事前に相談し、必要な手続きを確認することが重要です。
出席扱いの申請は学校側の判断による部分が大きいため、事前にしっかりと話し合いを行い、申請に必要な書類や条件を把握しておくとスムーズに進めることができます。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
出席扱いの申請には、学校や自治体によって異なる条件が設定されていることがあります。
そのため、まずは担任の先生や学校側に相談し、どのような書類が必要なのかを確認しましょう。
一般的には、以下のような書類が求められることが多いです。
– 学習計画書:どのように学習を進めるかを示す書類
– 学習記録・レポート:学習の進捗を証明するための記録
– 学校との面談記録:保護者や学校が不登校の状況を把握し、話し合った内容を示すもの
学校によっては、すららの学習履歴を提出することで、出席扱いの判断がしやすくなるケースもあります。
こうした点についても、事前に確認しておくことが大切です。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
不登校の理由によっては、医師の診断書や意見書の提出が求められることがあります。
これは、学校側が「なぜ登校できないのか」「どのような学習環境が適しているのか」を判断するために必要とされるものです。
必ずしもすべてのケースで診断書が必要なわけではありませんが、特に精神的な負担や発達障害などの理由で不登校になっている場合は、用意しておくとスムーズに申請が進む可能性があります。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
学校側が出席扱いを認める際に、子供の状況を客観的に説明できる資料があると、判断がしやすくなります。
特に、心の問題や発達障害が関係している場合、医師の診断書を提出することで、学校側が「自宅での学習が適している」と納得しやすくなります。
診断書の提出が必要かどうかは、学校に相談して確認することが大切です。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
医師の診断書や意見書を用意する場合は、子供の状態を詳しく説明し、「学習の継続が望ましい」という内容を明記してもらうことがポイントです。
精神科・心療内科・小児科などの専門医に相談し、不登校の原因や子供の状態について説明した上で、適切な文書を作成してもらいましょう。
この診断書があることで、学校側も「学習を継続することが必要である」と判断しやすくなり、出席扱いの承認がスムーズに進むことがあります。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
出席扱いとして認めてもらうためには、学習を継続している証拠を学校に提出することが大切です。
すららでは、学習の進捗を記録するシステムが整っており、保護者や子供が手作業で学習記録を作成する手間を省くことができます。
この学習記録を活用し、学校側にしっかりと学習していることを示すことで、出席扱いの承認を得やすくなります。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららでは、学習の進捗を可視化する「学習進捗レポート」を作成することができます。
これをダウンロードし、担任の先生や校長先生に提出することで、「どの教科をどれだけ学習したのか」「学習のペースはどうなっているか」といった情報を明確に伝えることができます。
学校側が出席扱いを判断する際には、こうした客観的なデータが非常に重要になるため、忘れずに提出しましょう。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
学習記録とともに、学校によっては「出席扱い申請書」の提出を求められる場合があります。
これは、学校が正式に「この子供の自宅学習を出席扱いとする」ことを判断するための書類で、必要事項を記入して提出する必要があります。
多くの場合、学校側が作成しますが、保護者がサポートしながら必要な情報を提供することが求められます。
学校の指示に従い、適切に対応しましょう。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
出席扱いの最終判断は、学校長(校長先生)の承認によって決まります。
自治体によっては、教育委員会の承認が必要になる場合もあるため、学校としっかり連携して進めることが大切です。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
学校での出席扱いの判断は、最終的に学校長(校長先生)が承認することで決定されます。
提出した学習記録や申請書の内容をもとに、学校側が「自宅学習が適切に行われているか」「出席扱いとして認めるかどうか」を判断します。
すららの学習記録がしっかりと管理されていること、学習計画が明確であることが、承認の大きなポイントになります。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
自治体によっては、出席扱いの判断を学校だけでなく、教育委員会の承認が必要になるケースもあります。
その場合は、学校側と連携しながら、教育委員会への申請を進めることが求められます。
必要な書類や手続きについては、学校に確認しながら進めるのがスムーズです。
保護者が直接教育委員会に申請するのではなく、学校を通じて手続きを進めることが一般的なため、担任や校長先生と相談しながら対応していきましょう。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します
学校に通えない状況が続くと、「このままで大丈夫なのか」「学習の遅れが心配」など、子供だけでなく保護者も不安を感じることが多いです。
そんなとき、すららを活用することで、オンライン学習を出席扱いとして認めてもらえる可能性があります。
出席扱いになることで、内申点への影響が軽減されたり、進学の選択肢が広がったりと、多くのメリットがあります。
また、継続的に学習する環境が整うことで、「勉強が遅れている」という不安も和らぎ、子供の自己肯定感を守ることにもつながります。
さらに、学校・家庭・すららコーチの連携によって、保護者の負担が軽減される点も大きな利点です。
ここでは、すららを活用して出席扱いを認めてもらうことのメリットについて詳しく紹介します。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
学校では、出席日数が成績評価の一部として影響を与えることが多いため、不登校の期間が長くなると、内申点の低下につながる可能性があります。
しかし、すららを活用して出席扱いとなれば、一定の出席日数が確保されるため、内申点の低下を防ぐことができます。
内申点は、中学や高校の進学時に重要な判断基準となるため、出席扱いの制度を活用することは将来の進路を広げるうえでも大きなメリットとなります。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
内申点は、学力だけでなく「出席状況」も評価の対象となります。
特に公立高校では、出席日数が一定基準を下回ると評価が下がることがあり、長期間の欠席が進学に影響を与えるケースもあります。
しかし、すららを活用して出席扱いとして認められれば、欠席扱いの日数が減るため、内申点の低下を防ぐことができます。
これにより、「不登校だから成績が不利になる」といった不安を軽減することができます。
中学・高校進学の選択肢が広がる
内申点が安定することで、進学の選択肢が広がるというメリットもあります。
高校入試では、内申点が重要な判断材料となるため、出席日数が少ないと不利になりがちです。
しかし、すららを活用して学習を継続し、出席扱いとして認めてもらえれば、進学時の評価にプラスの影響を与えることができます。
さらに、オンライン学習を通じて学力を維持することができれば、より上位の学校への進学も目指しやすくなります。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校が続くと、子供自身が「授業についていけなくなるのではないか」「もう取り戻せないかもしれない」と強い不安を感じることがあります。
しかし、すららは無学年式の学習システムを採用しているため、学校の授業とは異なるペースで、自分に合った学習を進めることができます。
これにより、遅れを気にせずに学び続けることができ、安心して勉強を続けられる環境が整います。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
すららでは、学年に関係なく必要な単元から学習を進めることができます。
そのため、「今の学年の授業についていけない」という焦りを感じることなく、理解できるレベルから無理なく学習を続けることができます。
例えば、算数や国語など、苦手な単元を前の学年に戻って復習することも可能ですし、得意な科目はどんどん先に進めることもできます。
この柔軟な学習スタイルによって、学習の遅れを取り戻しやすくなります。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
不登校が続くと、「勉強ができなくなった」「みんなと同じように学べていない」という思いから、子供の自己肯定感が下がることがあります。
しかし、すららを活用することで、自分のペースで学習を続けられる環境が整い、「できた!」という成功体験を積み重ねることができます。
学習の進捗が可視化されることで、子供自身が成長を実感しやすくなり、「自分は学べるんだ」という自信につながります。
メリット3・親の心の負担が減る
不登校の子供を持つ保護者は、「このままで大丈夫だろうか」「勉強が遅れてしまわないか」など、さまざまな不安を抱えることが多いです。
しかし、すららを活用することで、学校・家庭・すららコーチの三者が連携しながら学習をサポートする体制が整うため、保護者が一人で抱え込む負担が軽減されます。
特に、すららコーチが学習計画を立て、進捗を見守ってくれることで、保護者が細かく学習を管理する必要がなくなり、精神的な余裕が生まれます。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
すららでは、専任のコーチが学習の進め方をサポートしてくれるため、保護者がすべてを管理しなくても、子供が自分のペースで学習を続けることができます。
さらに、学校側と連携して出席扱いの申請を進める際も、すららの学習記録やレポートを活用することで、学校とのやり取りをスムーズに進めることが可能です。
これにより、「どう対応すればいいのかわからない」という保護者の不安を軽減し、安心して子供の学習を見守ることができます。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します
すららを活用して出席扱いを認めてもらうためには、いくつかの注意点があります。
文部科学省のガイドラインでは、一定の条件を満たせばオンライン学習を出席扱いとして認めることが可能ですが、最終的な判断は学校や教育委員会に委ねられています。
そのため、学校側との丁寧なコミュニケーションが必要であり、場合によっては医師の診断書や意見書の提出が求められることもあります。
こうした点を事前に理解し、適切な対応を取ることで、スムーズに申請を進めることができます。
ここでは、出席扱いを認めてもらうための具体的な注意点について詳しく解説します。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
すららを利用した出席扱いの申請を進めるには、まず学校側の理解を得ることが不可欠です。
学校によっては、オンライン学習による出席扱いの制度について詳しく知らない場合もあるため、しっかりと説明することが大切です。
特に、担任の先生だけでなく、教頭や校長とも早めに相談し、学校全体として前向きに検討してもらえるように働きかけることが重要です。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
すららは、文部科学省が推奨する「ICTを活用した学習支援」に対応している教材ですが、学校側がその事実を十分に把握していないこともあります。
そのため、出席扱いとして認めてもらうためには、「すららは文科省のガイドラインに準拠している学習ツールである」ということを丁寧に説明する必要があります。
学校側にとっても、適切な学習環境が整っているかどうかを確認することは重要なポイントになるため、すららの特徴や学習の仕組みについて、具体的な情報を伝えることが大切です。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
学校側に説明する際は、すららの公式サイトからダウンロードできる資料や、学習の進め方が分かるパンフレットを持参すると、より理解を得やすくなります。
口頭だけで説明するよりも、具体的な資料を提示することで、学校側も安心して判断しやすくなります。
また、担任の先生だけでなく、教頭や校長にも早めに相談し、学校全体としてどのような対応が可能かを検討してもらうことが重要です。
特に、出席扱いの申請は校長の判断による部分が大きいため、できるだけ早い段階で話を進めておくとスムーズに手続きが進められます。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
出席扱いの申請において、不登校の理由によっては医師の診断書や意見書の提出が求められることがあります。
特に、体調不良や精神的な理由で学校に通えない場合、学校側が「学習の継続が可能かどうか」を判断するための資料として、医師の意見書を重視することがあります。
そのため、必要に応じて、早めに医療機関に相談し、適切な書類を用意することが大切です。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
学校側は、出席扱いの判断をする際に「なぜ学校に通えないのか」「家庭での学習が継続できるか」といった点を重視します。
特に、体調不良や精神的な理由で不登校になっている場合、単なる「親の申し出」だけではなく、専門家の意見が必要になることがあります。
そのため、心療内科や小児科など、子供の状態を把握している医師に相談し、診断書や意見書を用意することで、学校側の理解を得やすくなります。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
医師の診断書を作成してもらう際は、「出席扱いの申請に必要な書類を作成してほしい」と具体的に伝えることが大切です。
医師によっては、どのような内容を書けばいいのか分からない場合もあるため、「家庭学習を継続できる状況であること」や「学校の授業に代わる学習手段としてすららを活用していること」を明確に説明し、診断書に記載してもらうようにするとよいでしょう。
また、診断書の発行には時間がかかる場合もあるため、早めに相談しておくことが重要です。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
診断書には、「家庭での学習が継続可能であること」「学習意欲があり、すららを活用して学んでいること」を明記してもらうと、学校側の判断がスムーズになります。
医師に相談する際には、家庭でどのように学習を進めているのか、子供がどのような意欲を持っているのかを具体的に説明し、「学習を継続することが精神的な安定にもつながる」といった視点で診断書を書いてもらうとよいでしょう。
こうした内容が記載されていることで、学校側も「家庭学習が適切に行われている」と判断しやすくなります。
注意点3・学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
すららを利用して出席扱いを認めてもらうためには、学習の質と量が「学校の授業に準ずるもの」と判断される必要があります。
単に自宅で学習しているだけではなく、学校のカリキュラムに沿った学習を計画的に進めていることを学校側に示すことが重要です。
特に、学習時間や科目のバランスを考慮し、学校の授業と同じように幅広い内容を学ぶことが求められる場合が多いため、注意が必要です。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
学校側が出席扱いを認めるためには、すららを利用した学習が「単なる自習」ではなく、学校の授業と同等の内容であることを示す必要があります。
たとえば、好きな科目だけを学習していたり、市販の問題集を解くだけでは、学校の授業と同じ水準とはみなされにくくなります。
そのため、すららの学習記録を活用し、学校の指導要領に基づいた学習が行われていることを明確にすることが大切です。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
学校での授業時間と大きくかけ離れた学習時間では、出席扱いとして認められにくくなることがあります。
そのため、目安として1日2〜3時間程度の学習時間を確保することが望ましいとされています。
すららでは、短時間のスモールステップ学習が可能なため、集中力が続きにくい場合でも、学習時間を分割して取り組むことで、学校に準じた学習時間を確保しやすくなります。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
出席扱いの申請では、特定の科目に偏らず、全教科をバランスよく学習していることが求められることがあります。
国語・数学・英語といった主要教科だけでなく、理科・社会も含めて学習を進めることが望ましいです。
すららでは、無学年式のカリキュラムを採用しているため、各教科を自分のペースで進めながら、バランスよく学習を進めることが可能です。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
出席扱いを認めてもらうためには、学校との定期的なコミュニケーションが欠かせません。
オンライン学習を活用していることを学校側に理解してもらい、学習状況を適切に共有することで、学校側が出席扱いの判断をしやすくなります。
定期的に進捗を報告し、必要に応じて面談などに対応することで、学校との信頼関係を築くことが大切です。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
多くの学校では、出席扱いを認める条件として、家庭と学校が連携しながら学習状況を共有することを求めています。
そのため、すららの学習記録を活用して、どのような学習を行っているかを定期的に報告することが必要になります。
学校側が学習の進捗を把握できるようにすることで、出席扱いを認める判断がしやすくなります。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
学校側への学習状況の報告方法として、すららの学習レポートを活用するのがおすすめです。
すららでは、学習時間や進捗を記録する機能があり、それをレポートとしてダウンロードできます。
これを月に1回程度学校に提出することで、学校側が学習の状況を確認しやすくなり、出席扱いの判断をスムーズに進めることができます。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
学校によっては、出席扱いを認める前に、家庭訪問や面談を実施する場合があります。
これは、子供の学習環境を確認し、学習が適切に進められているかを確かめるために行われることが多いです。
そのため、学校から求められた場合は、積極的に対応し、家庭学習の状況を丁寧に説明することが重要です。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
出席扱いを認めてもらうためには、担任の先生とのコミュニケーションが不可欠です。
月に1回の学習レポート提出だけでなく、定期的にメールや電話で進捗状況を共有すると、学校側も学習の継続性を確認しやすくなります。
特に、子供の学習の様子や変化などを具体的に伝えることで、学校側の理解を深めることができます。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
学校ごとの判断だけでなく、自治体によっては教育委員会の承認が必要になる場合もあります。
学校側の指示に従いながら、必要な書類を準備し、適切な手続きを進めることが大切です。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
教育委員会に申請が必要な場合、学校と連携して必要な書類を準備することが重要です。
教育委員会では、オンライン学習をどのように活用しているか、学習の継続性が確保されているかなどを詳しく確認されることが多いため、学習計画や進捗レポートをしっかりと整えることが求められます。
学校と密に連絡を取りながら、スムーズに申請を進めることを心がけるとよいでしょう。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します
すららを活用して出席扱いを認めてもらうためには、学校側に「学習の継続性」と「学習の質」が確保されていることをしっかりと伝えることが大切です。
文部科学省のガイドラインでは、オンライン学習が出席扱いになる可能性があるとされていますが、最終的な判断は学校の校長先生に委ねられます。
そのため、学校側に納得してもらうためのアプローチが重要になります。
ここでは、すららを利用して出席扱いを認めてもらうための成功ポイントについて詳しく紹介します。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
学校側が出席扱いを認めるかどうかを判断する際、「前例があるかどうか」は大きなポイントになります。
もし、すでに他の学校で出席扱いが認められている事例があれば、「すららを使って出席扱いになった例がある」ということをアピールすることで、学校側の理解を得やすくなります。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
すららは全国の学校や自治体で導入されており、すでに多くの不登校の子供が出席扱いとして認められています。
そのため、学校側に対して「他の学校ではすららを活用して出席扱いになっている」という事実を伝えることが有効です。
具体的な事例を示すことで、学校側も「すららを使った出席扱い」が前例のないものではないと理解しやすくなります。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
すららの公式サイトには、出席扱いの実績や導入事例が紹介されています。
これをプリントアウトして学校に持参し、担任の先生や校長先生に説明することで、学校側の納得感を高めることができます。
特に、同じ地域や近隣の学校での実績がある場合は、より説得力が増します。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
学校側が出席扱いを認めるためには、「学習の継続性」だけでなく、「本人がどれだけ学習に取り組んでいるか」も重要なポイントになります。
子供自身の学習意欲をしっかりとアピールすることで、学校側の判断が前向きになりやすくなります。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
学習の意欲を伝える方法として、本人が書いた学習の感想や目標を提出するのも効果的です。
たとえば、「すららを使って○○を学んだ」「次は△△を頑張りたい」といった内容を学校に伝えることで、学校側に「本人が主体的に学習している」という印象を与えることができます。
これは、出席扱いの判断をする際の重要な要素となります。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
出席扱いの申請を進める過程で、学校との面談が行われることがあります。
その際、本人も同席し、「学習に取り組んでいること」や「今後の学習目標」について自分の言葉で伝えることができれば、学校側の印象は大きく変わります。
直接話すことで、「ただ家庭学習をしているだけでなく、継続的に学び続ける意思がある」ことを示すことができ、出席扱いとして認められやすくなります。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
出席扱いを認めてもらうためには、「学習が継続して行われること」が大前提になります。
そのため、最初から無理のある学習計画を立ててしまうと、途中で続かなくなり、結果的に学校側の信頼を得にくくなります。
本人のペースに合わせた無理のない学習計画を作ることが大切です。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
出席扱いが認められるためには、長期間にわたって学習を続けることが必要です。
そのため、最初からハードルの高い学習計画を立ててしまうと、途中で挫折する原因になってしまいます。
すららのスモールステップ学習を活用し、1日1時間から始めるなど、無理なく続けられる学習計画を立てることが重要です。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
すららでは、専任のすららコーチが学習計画をサポートしてくれます。
学習の進め方に悩んだ場合は、すららコーチに相談し、無理なく続けられるスケジュールを一緒に立ててもらうのがおすすめです。
コーチのアドバイスを取り入れることで、より現実的で実行可能な計画を作ることができ、学習の継続につなげることができます。
ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する
すららを活用して出席扱いを認めてもらうためには、すららコーチのサポートを最大限に活用することが大切です。
すららコーチは、学習計画の作成だけでなく、出席扱いの申請に必要なレポート作成や学習証明のフォローなども行ってくれます。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
出席扱いを申請する際、学校側に提出する「学習レポート」や「学習証明書」が必要になります。
すららコーチは、これらの書類作成をサポートしてくれるため、保護者の負担を軽減しながら、学校側への提出資料をしっかりと整えることができます。
コーチのサポートを受けながら、必要な書類を適切に準備することで、スムーズに出席扱いの申請を進めることができます。

すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
すららはうざいという口コミがあるの理由について、論じます。
すららは、その特性から様々な意見が出るものですが、なぜ一部の方が「うざい」と感じるのか、その背景にはいくつかの理由が考えられます。
まず第一に、すららの情報量の多さが挙げられます。
すららは、様々な情報を提供するため、その情報の多さが一部の方にとっては圧倒的に感じられることがあります。
さらに、すららはインタラクティブな要素も含んでおり、そのために時間を要することがあり、煩わしさを感じることもあるかもしれません。
他にも、個人の好みや使い方によって、うざいと感じる要因は異なるかもしれませんが、それぞれの背景や価値観によって、評価が分かれることも理解されるべきです。
すららは、人気のあるアプリケーションですが、その一方で批判も受ける要因があることを理解し、改善の余地があるかもしれません。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららの発達障害コースの料金プランについてお伝えします。
当コースは発達障害を持つ方々に特化したサービスを提供しており、料金面においても丁寧に計画されております。
まず、すららの発達障害コースでは、個々のニーズに合わせたカスタマイズされたサービスをご提供しております。
その為、料金プランは個人個人によって異なりますので、具体的な料金についてはお問い合わせいただくか、ウェブサイトをご確認ください。
また、当コースでは、利用されるサービス内容や頻度によっても料金が変動しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
安心してご利用いただけるよう、適切なプランをご提供いたします。
発達障害をお持ちの方々がスキルや自己肯定感を向上させ、充実したサポートを受けられるよう心掛けております。
関連ページ: すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
登校拒否や学校に行けない不登校の子供を抱えるご家庭にとって、教育の機会を提供することは重要です。
そんな中、すららのタブレット学習は不登校の子供たちにとって、出席扱いとなるのでしょうか。
すららのタブレット学習は、ユーザーのログイン情報で学習履歴や進捗状況を管理しており、教育機関もこれらの履歴を確認できる仕組みが整っています。
したがって、すららのタブレット学習を利用すれば、不登校の子供たちの学習時間や成果を正確に把握し、学校側でも出席として認めることが可能です。
また、タブレット学習は柔軟な学習スタイルを提供し、子供たちが自宅や外出先でも学び続けられる環境を整えることができます。
不登校の子供たちにとって、学び続ける機会を提供するすららのタブレット学習は、学校と連携して出席扱いとして位置付けることができる画期的な教育手段と言えるでしょう。
関連ページ: すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららをご利用いただき、誠にありがとうございます。
皆様から多く頂く質問の中で、「すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください」というお問い合わせを受けます。
こちらでは、すららのキャンペーンコードを利用する際の手順を詳しく説明いたします。
まず、すららの公式ウェブサイトにアクセスしてください。
デスクトップ、またはモバイルデバイスからアクセス可能です。
サイトにログインし、「アカウント設定」のページに移動してください。
ここで、画面に表示される「キャンペーンコード」の入力欄に、ご利用いただいたキャンペーンコードを入力してください。
次に、「適用する」ボタンをクリックすると、キャンペーンコードが適用されます。
適用後は、ご注文時や支払い時にキャンペーンが適用されます。
キャンペーンコードはご注文金額から割引が適用される場合もありますので、ご注意ください。
また、キャンペーンコードの有効期限にもご注意ください。
期限を過ぎた場合は、キャンペーンコードはご利用いただけませんので、ご注意ください。
キャンペーンコードの詳細や利用条件については、公式ウェブサイトの「キャンペーン」ページをご参照いただくか、お問い合わせください。
以上が、すららのキャンペーンコードを使う際の手順となります。
お客様のショッピング体験がより快適でお得なものになることを願っております。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
関連ページ: すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららを退会する方法についてお知らせいたします。
まず、退会手続きを行う際には、すららのウェブサイトにアクセスする必要があります。
ログイン後、マイページに移動し、アカウント設定メニューを開いてください。
その中に退会手続きの項目がございますので、そちらを選択してください。
その後、指示に従って必要事項を入力し、退会手続きを完了してください。
手続きが完了すると、すららの利用は終了となります。
退会に際して何かご質問がございましたら、すららのカスタマーサポートにお問い合わせいただければ幸いです。
ありがとうございます。
関連ページ: すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららをご利用いただきありがとうございます。
入会金および毎月の受講料だけでなく、追加料金などがかかるかどうかについてお尋ねいただきありがとうございます。
すららでは、入会金や受講料以外に、追加の料金は発生いたしません。
ご安心ください。
入会後に予期せぬ追加費用が発生することはございません。
お客様が安心してコースを受講いただけるよう、料金に関する明確な情報を提供しております。
ますますのご活用を心よりお待ちしております。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
1人の受講料を支払った場合、それを兄弟が一緒に利用することができるかどうかは、お支払いいただいた受講料によって異なります。
多くの場合、支払われた料金は1人につき1回の受講のみをカバーしており、他の家族や兄弟が同じ受講に参加することは通常認められていません。
兄弟全員が受講を希望する場合、それぞれの受講料を支払う必要があるでしょう。
そのため、複数の人が使うことが可能かどうかは、事前に受講料の利用規約やルールを確認することが重要です。
兄弟で受講をご希望の場合は、受講料について事前に詳細を確認し、適切な手続きを行うようにしてください。
すららの小学生コースには英語はありますか?
「すららの小学生コースには英語はありますか?」というご質問ありがとうございます。
当校の小学生コースには、英語の授業がございます。
英語は、世界的に重要な言語であり、早い段階から学習することが有益とされています。
当校のプログラムでは、基礎からしっかりと英語を学ぶことができるカリキュラムを備えており、生徒たちがスムーズに成長できるようサポートしています。
ぜひ、英語を学びたいお子様におすすめのコースです。
質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららを活用する際、専門のコーチがどのようなサポートを提供してくれるか気になる方も多いかと思います。
すららのコーチは、熟練した専門家であり、生徒の目標達成に向けて多岐にわたるサポートを提供しています。
まず第一に、すららのコーチは生徒一人ひとりのニーズや目標に合わせたカスタマイズされた指導を行います。
生徒の現在のレベルや学習スタイルに合わせて、最適な学習方法や学習計画を立て、最良の結果を引き出すお手伝いを致します。
また、すららのコーチは生徒の学習進度を常にモニタリングし、適切なフィードバックやアドバイスを提供してくれます。
生徒の強みや課題を的確に把握し、学習効果を最大限に高めるためのサポートを行います。
さらに、すららのコーチは生徒とのコミュニケーションを大切にし、質問に丁寧に回答したり、学習上の疑問や悩みに応じたサポートを行うことで、生徒が安心して学習に取り組むことができる環境を提供します。
すららのコーチからは、熱心なサポートや的確な指導を受けることができます。
生徒一人ひとりが目標達成に向けて最善のサポートを受けられるよう、すららのコーチがあなたを全力でバックアップします。
参照: よくある質問 (すらら公式サイト)

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ
今回の記事では、不登校の生徒が出席扱いになるための制度や申請手順、注意点についてまとめました。
不登校でも出席扱いになるためには、正式な手続きと条件をクリアすることが重要です。
まず、学校や教育委員会などに申請を行い、その手続きに従うことが必要です。
また、不登校の理由や期間、補習の履修状況なども考慮されることがありますので、事前によく確認しておくことが大切です。
出席扱いに関する注意点としては、申請手続きを怠らないことや必要な書類をきちんと揃えることが挙げられます。
さらに、不正確な情報を提出したり、手続きを疎かにすると出席扱いが認められない場合もあるため、慎重に行うことが必要です。
不登校でも出席扱いになることで、学業や将来において支障が少なくなることが期待されますが、そのためには正確かつ丁寧な手続きが求められます。
不登校の生徒が出席扱いになるための制度や申請手順、注意点についての理解を深めることで、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。
不登校の状況や学業に関わる懸念を抱えている場合でも、適切なサポートを受けながら問題解決に取り組むことが大切です。
出席扱いに関する情報を活用し、生徒一人ひとりが安心して学びを続けられる環境づくりに貢献していきましょう。

